いくら博捜しても求める資料が見つからないことがほとんどなのだが、ふとしたことで、思いがけない資料が見つかることが稀にはあるものである。先ごろ別件で岐阜辺を調査中に、八百津の大仙寺で、室町期の写本一冊を寓目した。表紙には「大仙住持太雅和尚墨蹟」とある。太雅は、美濃大仙寺開山、東陽英朝(1428〜1504)の法嗣で同寺二世となった太雅耑匡である。同寺には太雅筆の他の写本もあり、この写本の筆跡が太雅であると確認できる。
写本は四十四丁。その内容は、文明五癸巳年(1473)から文明十一己亥年(1479)までの七年間にわたる百三十八の詩文が年次順に記載されている。作者は相国寺の僧で、これらの詩文はすべて、東関という喝食に宛てられたもので、一読して艶詞とわかるものである。その中に仙翁花について書かれた詩文が九件あるが、中でもことに注目すべきは、いくつかのやや長い引(序)の中で書かれている、仙翁花についての記事である。
その前に問題なのは、この詩文の作者が誰か、である。文明期に相国寺にいた僧でまず思い浮かぶのは、この時期の五山を代表し、つとに詩文で名の聞こえた横川景三(1429〜1493)である。
この写本の中には、「啓札(啓箚)」とよばれる四六体の文が二十おさめられている。「啓箚」とは「禅林で年中行事の節々に儀礼的にとり交わされ、または美少年に密に意を通ずるために作成される書状」(玉村竹二、『五山文学新集』第一巻、解説、990頁)のことであるが、実は、この「啓箚」のすべてが『横川景三集』に載るものと一致する。また横川の語録には月関の名がしばしば出るので、横川との関係も裏づけられる。よってこの写本の原著者は横川景三としてよい。
この写本に載る「啓箚」以外の詩文は、これまでに判明している横川景三の語録、あるいは『翰林五鳳集』には見えない。作者も判明したことなので、この写本をかりに『小補艶詞』と呼ぶことにする。小補軒は相国寺山内の横川の住坊の名である。
さて、当面の主題は、この『小補艶詞』にある引・序に出る仙翁花のことである。
まず[三九](芳澤による整理番号)の「仙翁花を贈る詩、并びに序」(文明七乙未[一四七五]の七夕)には次のようにいう。
……世に伝う、仙翁は本朝の花にして大唐に之無しと。或いは丹波に産すと曰い、或いは嵯峨に産すと曰う。將た然りと信ぜんか。……按ずるに、唐の明皇、方士に命じて貴妃神を東海の中に致さしむ。蓬莱山に到るに、碧衣の侍女有り。延 き入れて妃に見えしむ。妃、方士に謂いて曰く、驪山宮の七夕に、上、女牛の事を感じ、蜜(密)に心願を相誓って、世々夫婦たらんと云々。本朝の熱田の廟は、乃ち蓬莱なり。神は乃ち貴妃なり。方士の来たらしむる所なり。宋学士が日東曲に謂える有り、曰く、国に楊貴妃の祠有りと。其の曲に曰く、莫是仙山真縹緲、雪膚花貌主珠宮(是れ仙山にあらずや、真に縹緲なり、雪の膚 花の貌 、珠宮を主る)。是に由って之を観ば、仙翁花は則ち丹波に産せず、嵯峨に生ぜずして、熱田の蓬莱より来たれる者なり。
京都の嵯峨が仙翁花発祥の地であるとの説は、すでに見たところであるが、横川はここで別の考えを述べている。横川のいうところを簡単にいえば、尾張の熱田神宮の神は楊貴妃であり、その化身が仙翁花である、というのである。
中国でいう神仙の三嶋のひとつ蓬莱が日本にあるとの俗説は、『仙伝拾遺』など中国で古くからあり、それに呼応して、日本では熊野、富士山、白山、住吉などを蓬莱とする説が出たが、熱田神宮もまた蓬莱嶋とされるのである。
この熱田神宮の神が化身となったのが唐の楊貴妃であるという俗説が古くからあった。その内容は次のようなものである。唐の玄宗皇帝が日本を侵そうとしたので、熱田明神が楊貴妃となって生れ、玄宗の心を蕩して世を乱し、日本をうつのをやめさせた。やがて楊貴妃は馬嵬で殺されたが、玄宗は悲しみにたえず、方士をつかわして、貴妃の霊をさがし尋ねさせたところ、蓬莱嶋にあるとのこと、その蓬莱が熱田である、というものである。いま横川は宋学士(宋景濂)の日東曲をその証拠として引いているのである。
[六八]「仙翁花を贈る詩并びに序」(文明八丙申年[1476]七月五日)
……丙申の七月、仙翁花、地を絶して之無し。凡そ公館豪家、優鉢 の遇い難きが如くす、況んや我が輩に於てをや。今日偶たま客有り、此の花を恵まるる者、吁仙なるか凡なるか、夢なるか夢に非ざるか。喜び言う可からず。……謹んで小詩を賦し花を副え、月関美丈が研右に投じ奉る。実に星夕前二日なり。
この夏(1476年)は、何らかの理由で不作だったらしい。まったく仙翁花が出回らなかった。洛中の貴顕にも届かないのだから、私のところに到来するはずはないだろう、とあきらめかけていたところへ、思いがけず到来品があったので、さっそく、それを月関美丈に届けたのである。
[九六]文明九丁酉年(1477)五月上旬の詩序、
……近時、吾が邦に花有り、仙翁と曰う。而して蓮と其の時を同じうす。仙風道骨、紅裙翠袂、溽暑の為に染まず。時の君子の騒乱の世に処して始終如一なる者と、并せ案ず可し。……
丁酉の歳、余が所居の傍に、寸地を規し竹を縛って籬と為し、手づから仙苗を移し、花を養うこと賢を養うが如し。旦 に視ては暮 に撫で、已に去って復た顧す、郭橐駝 に類 する者有り。春より夏に至り、蟠桃の花を著くるを待つが如し。謂っつ可し勤めたりと。今日、忽ち一両点の花を著く。苗にして秀づる者なり。喜び言う可からず。持して以て月関尊契に贈る。……
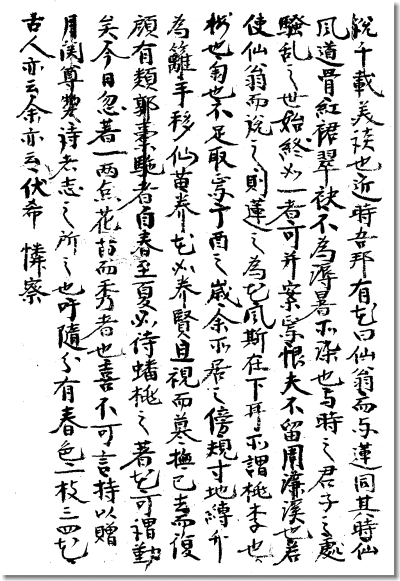
前年の七夕には、仙翁花はほとんど手に入らなかったこともあったのであろうか、横川は、今年になってついにみずから培養を始めた。自坊の一隅に畑をつくり、自ら仙翁花を育てた。毎日、その成長を楽しみにし、まだ咲かぬかまだ開かぬかと、朝な夕な、三千年に一度花開くという西王母の仙桃が花開くのを待つように待った。「旦に視ては暮に撫で、已に去って復た顧す、云々」は『古文真宝』におさめる、柳子厚の「種樹の
[九九]「仙翁花を贈る詩、并びに序」(文明九丁酉年[1477]五月上旬)
本朝に名花有り。春は則ち桜花、秋は則ち仙翁なり。予曽て之を南遊せる者に質 ぬ。説 って曰く、桜は、唐宋元明の詩中に之頗 し、而して未だ其の種を見ず。然るに仙翁は則ち諸詩に之無し。況んや其の種に於てをや。然らば則ち仙翁の本朝に産すること昭々たり。世に伝う、尾州に小蓬莱有り、熊野に徐福の祠有りと。想うに、神仙中の人、風塵表物、芳魂を此の花に託せる者か。尚ぶ可し。
横川は中国に留学した者に尋ねて、仙翁花が日本のみに産することを確認している。仙翁花を歌う者の多くが、わが国のみに産することを主張するのは、特徴のひとつである。そして、横川はここでも、それが熱田神の化身であることをいっている。
抑 そも、此の方の俗、七月七日に草花を闘 う戯れ有り、年々以て常と為す。而して仙翁、之が甲に居す。其の花たるや、秋風葉落の時に方って、紅顔は其の花、緑髪は其の葉、凡花野草の比に非ざる者、的 けん。五月五日、楚人が草を闘 えると、同日に語る可からず。吾が友社交接の間、闘花以て俗に效うと雖も、一茎両茎、詩を賦して以て之を贈り分かつ、宜なり。甚だしきときは、則ち之を筒にし之を束にす。多々益ます弁ず。一時の妝[壯か]観なり。
七夕の「草合わせ」は、『荊楚歳時記』に出るような百草を競う風習とはわけがちがう、というのである。わが禅林でも、七夕の日に花を贈り飾るのだが、これは単に俗習にならうのではない。わが「交義」の盟を同じくするものは、これに必ず詩を添えるのである、と。「宜なり」の一字に、ある種の自負が見てとれる。
「甚だしきときは之を筒にし、之を束にす」。仙翁花を贈る時には、花筒にさしたり、また何らかの包装をしたり、花扇の形に装飾することは前回に見たとおりである。
今歳丁酉の夷則、予、一枝も得ず、慨嘆措く莫し、高枕して只だ「河上仙翁去不回」の句を吟ずるのみ。忽ち剥啄の声を聞く。之を問うに、仙翁を携え来たる者なり。……此を持して以て月関美丈に献げ奉ると云う。詩一首、之に副う。実に星夕前一日なり。
前の[九六]で見たように、この年は自分で培養し、五月上旬には「一両点の花を著く」と喜んでいた。けれども、いま七月六日、最盛期なのに一枝も咲いていないという。横川の丹誠にもかかわらず、初めての培養はうまくいかなかったのであろう。「河上仙翁去不回」は崔曙「九日登望仙台呈劉明府」詩(三体詩におさめる)の一句。「剥啄」はコツコツ。来訪者の足音、あるいは戸をたたく音。「門前剥啄定佳客」というように、待たれる人の来訪をいう。
『小補艶詞』は文明五年から十一年、横川が四十五歳から五十一歳までに書かれたものである。この期間、横川は公務として将軍義政の外交文書を起草しているが、一方の私的な一面を窺う資料として、この艶詞は興味深い。
横川景三の学芸の師である瑞渓周鳳(1392〜1473)にも『臥雲子尺素』という艶詩集があり、『大日本史料』第八編之六、文明五年五月八日条に載録されている。子英という喝食に与えた「啓箚」である。その原本は内閣文庫に残されていて、瑞渓の印が捺されているところから見て、「啓箚」の原本と思われる。
艶詩は、心田清播や三益永因だけが専門としていたわけでなく、瑞渓周鳳や横川景三も作っていたのである。『翰林五鳳集』巻六十三、恋部にはその他の五山僧の名もある。室町禅林にあって「交義の道」は、文辞の才を賭した、それなりに真剣な行為であったのであろう。
室町禅林では、梅や水仙に始まり、一年中さまざまな花が贈答されているが、特別の意味をこめて(つまり、そのような詩詞を添えて)贈るならば、どの花もすべて「男色の花」になるわけである。けれども、これらの贈答花の中でも仙翁花、星節という特別な日に用いられるがために、特別な位置を占めたのであり、室町禅林ではいわば、男色(少年愛)のシンボルともいうべき存在になったのである。