ところで、これまでに検しえたところ、禅録に出るもっとも早いものは、仏通寺開山の愚中周及(1323〜1409)の語録『
仙翁、火を噴いて花魂を返し(仙翁噴火返花魂)
直に朝陽と化元を争う(直与朝陽争化元)
舜若神 、勝熱 の苦に遭い(舜若神遭勝熱苦)
赤心片々、乱りに掀翻 さる(赤心片々乱掀翻)
『五山文学全集』では第四句の「赤心」を「亦心」に作るが意不通、無著道忠の書写本(妙心寺龍華院蔵)にしたがって訂す。
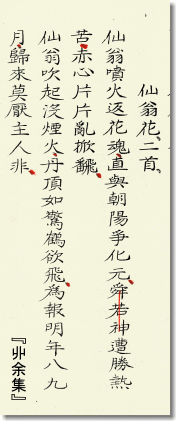
仙翁が火を噴いて、花魂となって蘇り、灼熱の太陽とその炎をきそう。舜若多神(虚空神)が炎にせめられ、千々に乱れる。勝熱婆羅門は善財童子があった知識(外道)の一人だが、いまは「火」の縁語として用いられていよう。炎を吐いて蘇った花魂はさながら太陽のようだというのである。「噴火(火を噴く)」とは、他の詩に例を見ない、何とも強烈な表現である。五祖法演禅師がその悟境をうたった詩の中に「華、鶏冠を
仙翁吹き起こす、没煙 の火(仙翁吹起没煙火)
丹頂、驚鶴の飛ばんと欲するが如し(丹頂如驚鶴欲飛)
為に報ず、明年八九月(為報明年八九月)
帰り来たるも主人の非を厭う莫かれ(帰来莫厭主人非)
「煙のない火(没煙火)」が、丹頂鶴となって飛び立たんばかりである。三四句はどのような事情をいうのか。作詩の時・場所にかかわるものと思われるが、今は未詳である。
愚中周及は初め夢窓下だった人であるが、同じ夢窓下の義堂周信(1325〜1388)や絶海中津(1336〜1405)の詩文集に仙翁花がまったく見えないのは、きわめて対照的である。
愚中は1341年に入元し、あしかけ十一年間、中国に滞在し、1351年、二十九歳のときに帰朝した。問題の仙翁花二首は何年に詠じられたものか。この二首の詩は『丱余集』巻一、偈頌部のかなり前の部分、二十二番目に載っている。偈頌部分は三十五丁あるが、その六丁目に出る。三首前には「哭仏通禅師」という偈がある。仏通禅師は愚中周及の中国での師である
『丱余集』巻一の偈頌は必ずしも厳密に時代順に配列されているのではないが、まったくアトランダムというわけでもない。断定は困難だが、収載の順序、および頌の内容からみて、晩年の作ではないように思う。さきに引いた、仙翁花がもっとも早く出る『愚管記』の記事は永和四年(1378)だったが、その年に愚中は五十四歳である。これより以前に詠まれた可能性もないではない。
愚中周及の法嗣に千畝周竹がいるが、その語録『也足集』(伊予西光寺蔵写本)にも仙翁花の詩が二首出る。
仙翁花の韻に和す(和仙翁花韻)
仙種何れの年にか此の花を降す(仙種何年降此花)
老禅一詠、詩家に越 す(老禅一詠越詩家)
艶粧自ずから是れ塵表を出づ(艶粧自是出塵表)
寧 ぞ群芳と級差を争わん(寧与群芳争級差)
この花はいつ仙界からこの世に下りたのか。老禅僧が詩とともにこの花を贈られた。この世のものとは思えぬ艶やかさは、他の花とはくらべものにならない。
等閑 に一枝花を拈起する句有り(有等閑拈起一枝花之句)
誰か仙翁を酔わせて草花に化 す(誰酔仙翁化草花)
紅粧 爛 熳 たり野僧が家(紅粧爛熳野僧家)
鷲峰 、拈じて一枝と作 し去る(鷲峰拈作一枝去)
五葉 聯芳 、猶お未だ差 わず(五葉聯芳猶未差)
「鷲峰拈作一枝」は釈尊の拈花の事を、「五葉聯芳」は、「一華開五葉」すなわち達磨の法のことをふまえたものである。
愚中と千畝の頌は、仙翁花の艶やかさは詠ってはいるものの、いずれも禅旨に関わるものであり、室町後期の仙翁花詩によく見られるような喝食を連想させる妖婉な表現はまったくないことに注目しておきたい。
それにしても、「火を噴く」ような花とはどのようなものなのか。実際に、花の色彩を見ずんばあるべからず。いよいよ本物を見たいと思うようになったのである。