|

シンポジウム
「戦後歴史学と宗教研究―教科書からこぼれおちたものを『民衆』・『宗教』からみる―」
登壇報告
|
|
2024年6月29日(土)、東京大学文学部法文2号館一番大教室(東京都文京区)にて、「戦後歴史学と宗教研究―教科書からこぼれおちたものを『民衆』・『宗教』からみる―」と題したシンポジウムが開催され、弊所副所長の飯島孝良が登壇致しました。
真宗大谷派親鸞仏教センターが主催したこの催しは、敗戦を契機に自立的な主体として注目された「民衆」が、皇国史観の反省の上に模索された戦後歴史学(戦後知)で重要な位置を占めるものとなったことに着目して企画されました。
「戦後の歴史学の中には、「民衆」を考えるうえで「宗教」の歴史に可能性を見出す者もみられた。例えば、「民衆の導き手」としての親鸞像を提示するものも台頭してきた(服部之總など)。また、いわゆる「東山文化」の研究は、戦前までは足利氏という「逆賊」の下に大陸文化をむやみに享受し公家文化を害するものと低く評価されたが、戦後はそれまで虐げられていた層が技芸で下剋上的に台頭した新奇の文化として、却って高く評価されることとなった(芳賀幸四郎など)。或いは、新宗教における「お筆先」などが科学研究の対象ではないといわれるなかで、その思想史的な重要性をどう見出せるかを研究しようとする動向も、「民衆」とかかわる宗教に注目した流れにあるものといえる(安丸良夫など)。とはいえ、こうした動向は、今日の歴史学で中心に位置しているとは言い難い。それはなぜなのだろうか」(開催趣旨文より)。
教科書の規範的な記述のなかでは、歴史の主体は政治の担い手であることが多く、文化や宗教は中心からは追いやられがちになっていることがままみられます。むしろ、戦後は文化や宗教こそが「民衆」の姿を描く上で重要な材料なのではないか、と考えられたともみられます。こうした点を、シンポジウムで問い直すこととなりました。
こうした問題意識の下、飯島からは「芳賀幸四郎からみる戦中/戦後の仏教史(禅文化史)を手がかりに」と題して発表しました。

まず、『元亨釈書』など中世日本の仏教史書でも高く評価された禅宗とその文化が、戦中から戦後にかけてどう評価されていたのかを見直しました。仏典や漢籍など大陸由来の文明を受容しながら日本の禅僧や公家や武士が独自の日本文化を形成するに至った「東山文化」が論じられ、戦後の歴史学において禅宗と日本文化を研究することが大きなトピックとなっていった趨勢を、「東山文化」の研究で知られた芳賀幸四郎(1908~1996)の論述を軸にして整理していきました。皇国史観においては、室町期のいわゆる「東山文化」は禅宗と強く関係したとされるとともに、天皇と対立した足利氏という「逆賊」の武士に支えられた文化などとされ、戦中まで低く評価されることがみられましたが、戦後には室町文化が技芸を身につけた「民」によって成立した「下剋上」の文化として論じ得た点が指摘されました。とくに芳賀が戦後に強調した中世史における「民」の存在は、主体としての「民」を確立しようとしていた戦後日本の民主主義的な流れと軌を一にしており、芳賀が旧来の国粋的な「国家」「天皇」を中心にした歴史叙述と異なる方法を模索し、「民族の生命力」に着目した文化史を構想しようとしていたことが見出せると論じました。
続いて、浄土真宗本願寺派史料研究所研究員の近藤俊太郎氏からは、「服部之總の親鸞・蓮如論が問いかけるもの:戦後日本宗教史研究の一断面」と題した発表が行われました。

近藤氏は、服部之總(1901~1956)が親鸞の公式的伝記たる『本願寺聖人親鸞伝絵』やその後の教団史における親鸞像・蓮如像と向き合い、とりわけ戦時下に親鸞を護国思想的に解釈してきた歴史との対決を試みたと指摘されました。また、本願寺の正史とは異なる親鸞理解として服部が意識していたのがヘーゲル・三木清など「観念論諸哲学」との関係で論じられる親鸞であったものの、それらと異なって農民とともにある親鸞を描き出そうとしたことにも言及されました。そうして一向一揆を論じる服部の親鸞・蓮如論は、戦時下の天皇制国家とその宗教性、そしてそれに従属し続けた真宗のありかたを否定し、戦後日本という歴史的条件のもとで民衆が担いうる積極的役割があることを確認するものであった、と述べられました。
更に、東北大学大学院国際文化研究科GSICSフェローの繁田真爾氏からは、「安丸良夫の民衆史研究が問いかけるもの:歴史研究と宗教史研究の対話のために」と題した発表が行われました。

繁田氏は、安丸良夫(1934~2016)が民衆史という枠組のなかで「宗教」に注目したのは、近代化していく社会を「宗教」を通して深層から見つめようとしたためであったと指摘されました。安丸民衆史の代名詞でもある通俗道徳論も、宗教史(宗教文化)の考察が原点としてあったことにも言及され、その特異な論述の価値について再考を促しました。そして、安丸民衆史が、①「世俗の権威から自立した別の原理」を宗教にみようとしたこと、②もし歴史研究が近代社会の現象的な分析・記述の範囲を出なければ、それは「現状追認的な保守主義に結果しやすい」ことに警鐘を鳴らしていたことの二点を挙げながら、“近代史研究は宗教の問題を。宗教史研究は支配体制の問題を”、それぞれの視座からこぼれがちな問題を相互に認識・参照し、議論を突き合わせていくことが、歴史研究と宗教史研究の両者を架橋する出発点となり得るのではないか、と述べられました。
そして、ディスカッサントとして東京大学大学院人文社会系研究科教授の加藤陽子氏に御登壇頂き、全体にわたるコメントを頂戴しました。

加藤氏からは、芳賀の戦時中の論述をまとめた『東山文化の研究』と、1942年頃から中国やインドに対する日本側の観点が変化するなかで編纂された『大東亜史』(未完)とで、“外来文化を巧みに受容しながら日本独自の歴史と文化を形成した”という点で共通する意識があったのではないかという指摘がなされました。また、被搾取者である農民こそが能動的に歴史を動かす主体であると論じる服部の立場について、天皇制打倒論との関わりで問われました。更に、細部・周縁・亀裂に注目する安丸独自のコスモロジー論などについて言及され、戦前の公共圏で中心となっていた天皇を相対化する動性として当時の寺院が位置付けられていたのではないか、とも述べられました。三つの仏教史・宗教史に関わる発表と歴史学が交点を見出そうとする対論として、非常に刺激的なものとなりました。
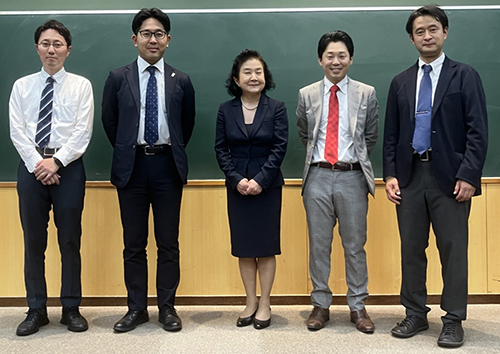
当日は多くの方に御参加頂き、長時間にわたり御聴講頂きました。ここに深く御礼申し上げます。
なお、この度のシンポジウムについて、中外日報(2024年7月5日付)でも報じられました。紙面ならびに以下のURLより御覧頂けます。
歴史記述 民衆・宗教の視点で再考 親鸞仏教センターシンポ:中外日報 (chugainippoh.co.jp)
|
 |