妙心寺退蔵院蔵の国宝「瓢鮎図」は禅美術を代表するものといってよい。幾多の禅美術が制作された応永年間の中でも記念碑的な作品とあって、これまで主として美術史家の注目を集めて来たのも当然のことであろう。
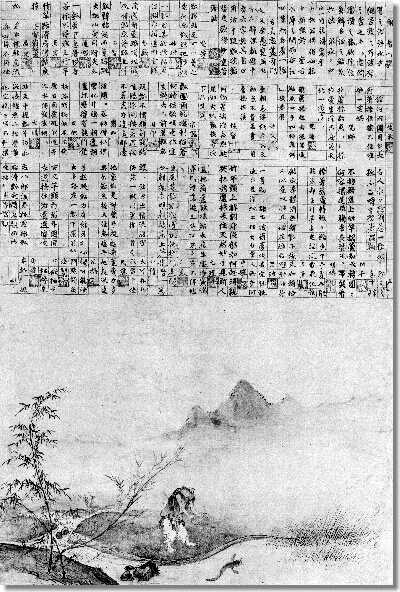
| 拡大画像(1000 x 1489、418KB)を表示 |
この絵画は足利義持の命によって画僧如拙が描いたもので、これに大岳周崇を始めとする三十一人の五山の禅僧による賛詩が寄せられている。三十二人の禅僧がこの詩画軸の制作にかかわっているのである。
この詩画軸の制作の経過や作者については、本稿では触れない。この絵の意味するところは何か。賛詩の検討を中心にしてその意味の解明を試みるのが本稿の目的である。
「瓢鮎図」賛詩の翻刻で、管見した中でもっとも古いのが『大日本史料』(1)、そして、その解釈を最初に明らかにしたのは福嶋俊翁氏(2)であり、その後、語学的により精密な解釈を試みたものが、島田修二郎・入矢義高監修『禅林画賛』(3)である。以上の賛詩の解釈をふまえて、「瓢鮎図」の持つ意味を、総合的に解明しようと試みたのが、島尾新氏の『瓢鮎図―ひょうたんなまずのイコノロジー』(4)である。
島尾氏は先行する成果をふまえながら、「瓢鮎図」の持つ意味の解明を試み、「これが禅の公案であるとは思えない」「〈ひょうたんでなまずをおさえる〉から宗教的な意味を引き出せるのだろうか」(島尾、前掲書13〜14頁)として、従来、漠然と「禅画」として扱われてきたことへ疑問を投げかけているが、明確な結論は保留されている。島尾氏のこの論は、大西廣氏の「瓢鮎図と瓢箪の呪術性」(5)という小論をふまえ発展させたもののようである。大西氏は、瓢鮎図が「禅の公案を絵にしたものである」という「通説」に最初に異をとなえたもので、「三十一人のお坊さんの賛を通読」して分かることは「禅の教訓どころか……一場の馬鹿騒ぎが演じられて」いることであり、そのテーマは「瓢箪の怪異、瓢箪の魔力」であるとしている(6)。
「ヴィジュアル・イメージは曖昧であり、さまざまな解釈可能性に対して開放されている」(島尾、前掲書103頁)ことは確かに事実である。一枚の絵に向かえば、幼稚園の小児から老人に至るまで、百人百様の感想が生まれるであろうし、直感的感性でどのように受け止めるかは自由勝手ではあるが、そのような感想は、その絵のもつメッセージの解明とはまた別の次元のことであろう。この奇妙な絵については、美術史家ばかりではなく、他の分野からもさまざまな感想が述べられ、解釈がなされて来ている。
かつて小林秀雄は、「妙な感じの現れた面白い絵である。……見れば見るほど変てこな処が、瓢箪なまずの傑作とでも言ふのであらうか」と、いささかとまどった感想を述べている(7)が、これは率直かつ素朴な印象を述べたものとすべきであろう。また、民俗学からも注目されるところとなり、飯島吉晴氏は、瓢箪で水神である鯰をおさえる構図であるとする(8)。ごく最近では、やはり民俗学の吉野裕子氏が島尾氏の図像解釈を利用しつつ自身の五行説によって、義持が父の義満を皮肉るために作らせた諷刺画であるという、まったく独自の解釈を展開している(9)。
実に多様で且つ任意な解釈が行なわれているわけであるが、その最大の理由は禅の側からの説明が消極的であったことであろう。この詩画軸には都合三十一人の禅僧による賛詩があり、そこにはかなりの情報が盛り込まれているはずなのに、そのことの解明が十分になされて来なかったのではないか。これが禅画であるならば、そのことを説明する試みがあってしかるべきであったのだが、この方面の研究はきわめて零細であり、それがこの詩画軸の解釈をいっそう混乱させる一因となって来たのではないかと考える(10)。
結論を先取りすることになるが、私は、瓢鮎図の企画するところは禅の本旨以外の何ものでもなく、すぐれて禅的なメッセージを詩画にしたものに他ならないと考える。そのテーマは何か。心である。心(鮎)を心(瓢箪)でとらえるということである。禅は仏の心印を直伝する宗旨であるゆえに仏心宗といわれる。「禅とは心の名なり、心とは禅の体なり」(11)ともいわれる。禅のテーマはつねに心である。
達磨と二祖慧可(神光)の問答がある(『伝灯録』巻三、達磨章)。
光曰く、諸仏の法印、聞くことを得べけんや。この問答によって、二祖慧可は達磨から付法される。すなわち、これが禅宗の始まりとなる。以降、禅宗においては常にこの心が問題となる。
師曰く、諸仏の法印は人より得るに匪 ず。
光曰く、我が心未だ寧 からず、乞う師、与 に安んぜよ。
師曰く、心を将 ち来たれ、汝が与 に安んぜん(将心来与汝安)。
曰く、心を覓 むるに了 に得可からず(覓心了不可得)。
師曰く、我れ汝が与 に心を安んじ竟 んぬ(我与汝安心竟)。
三祖
これらの例における「覓心了不可得」「将心用心、豈非大錯」「念念馳求心」「求心歇処」「三界無法、何処求心」というところを主題としたものであろうと考える。
このような結論は、以下で逐一見てゆくように、主として賛詩の検討から導かれるものであるが、画もまた同じ意図で表現されたものである。
ヴィジュアル・イメージの曖昧さに比すれば、漢字で表現された詩文の場合、意味するところはより明晰である。ことに五山のように、厳格な典拠に基づく作詩が教養の共通認識となっていた時代においては、詩文が曖昧であることはあり得ないはずである。意味が不明確に思われるのは、むしろ、ともすれば、当時は共通認識となっていた教養の厖大な蓄積を我々が知らないことに起因することが多い。
したがって本稿では、まず賛詩の意味の解明を第一義とする。そのために、これまでの翻刻も再検討し、剥落破損部分の検討推論をも試み、しかるのちに、賛詩そのものの意味を考える。「そこに語られていない〈意味〉を探るのは、いずれにしても〈深読み〉であることを免れない」(島尾前掲書54頁)からである。
上に言った『禅林画賛』は、「(賛は)その画を観た同時代者によって発せられた最初の言葉、最初の証言である」(該書の序)という観点から、禅林美術を画と賛の両面から解釈・鑑賞しようという趣旨で始められた画期的な試みであった。しかしながら、その賛文解釈部分に限っていえば、少なからぬ問題点があり、そのことは既に拙稿で述べたところである(12)。本稿はいわばその続編であり、主として、『禅林画賛』における解釈を批判的に再検討するものである。『禅林画賛』における賛詩の誤釈が、大西氏のいう「禅の教訓どころか……一場の馬鹿騒ぎ」といった誤解の原因になっているからである。
(以下、31の賛詩についての詳細な検討が続きますが、お急ぎの方は、直接、「画賛の意味するところ」へ読み進んで下さい)。
初出『禅文化研究所紀要 第26号』(禅文化研究所、2002年)