布鼓 〔解説〕
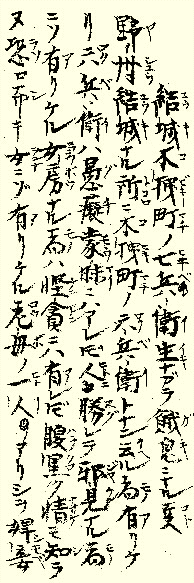 全五巻、二十三話の因縁話を収録する。底本には、宝暦三年(1753)、京都、吉田屋三郎兵衛、日野屋半兵衛の刊本(加藤正俊氏蔵)を用いた。これは『布鼓』(巻之一)と『再鞔布鼓』(巻之二~五)の二部分に分かれる。
全五巻、二十三話の因縁話を収録する。底本には、宝暦三年(1753)、京都、吉田屋三郎兵衛、日野屋半兵衛の刊本(加藤正俊氏蔵)を用いた。これは『布鼓』(巻之一)と『再鞔布鼓』(巻之二~五)の二部分に分かれる。
『布鼓』(不孝ノ子ニ贈リシ書)は白隠が三十歳の時に書いたもので、『再鞔布鼓』はのち、延享四年、禅師が六十三歳の時に加えたものである(「布つゞみの序」)。「再鞔」は鼓を張り替えるという意である。
上の刊本の原本と思われる白隠自筆の写本も残されている(白隠の生家である長澤信義氏蔵)が、話の数はこれより少ない。
この写本の末の紙貼付には「維時享保第九戊戍六月吉旦 御経司甲斐国産武田勇源其信謹而背工ス」とある。
享保九年(1724)は戊戍ではなく甲辰である。享保九年が正しければ、白隠四十歳。また戊戍が正しければ、享保三年(1718)、白隠三十四歳ということになる。
すなわち、三十四歳もしくは四十歳のときに、この写本が製本されたというのであるから、少なくともこれ以前、すなわち三十歳代には、すでに『布鼓』の原本は書かれていたことになる。字体も若書きに見える。
また『布鼓』巻之一の別本である『諌言記』という写本も伝わる(禅文化研究所資料室蔵。白隠の自筆ではない)。
そして、龍吟社版『白隠和尚全集』には、本書より少ない十四話が収録されていて、その解題には「延享四年丁卯小春の自筆刻本に依れり」とある。延享四年(1747)だから、本書の底本に先立つこと六年ということになるが、この版本は未見である。
上の四者の関係を表にすれば、次のようになる。 の数字は編成順。
| 各巻ごとの小題 |
布鼓
丁数 |
全集 |
長沢本
丁数 |
諫言記
丁数 |
| 布鼓 卷之一 |
| 布つゞみの序(延享第四丁卯) |
序1丁オ |
 |
 |
 |
| 布鼓 巻之一 |
 |
 |
 |
 |
不孝ノ子ニ贈リシ書 |
1丁オ |
1 |
1 1丁オ |
1 6丁ウ |
泉州津久見の富豪の子 |
1丁ウ |
1 |
1 1丁ウ |
1 7丁オ |
| 唐土漢陰の恕亮 |
5丁オ |
1 |
1 3丁ウ |
1 10丁ウ |
| 再鞔布鼓 |
 |
 |
 |
 |
| 父ヲ害シケル斧ノ柄、両ノ手ニ… |
16丁オ |
2 |
2 6丁ウ |
2 15丁ウ |
| 姑蘇村ノ安二、自ラ頭ヲ打チ割ル事 |
19丁オ |
3 |
3 8丁ウ |
3 19丁オ略 |
| 不孝ノ船頭、鰐ニ見入レラルヽ事 |
22丁ウ |
4 |
4 11丁オ |
 |
| 胎衣ヲ煮テ母ニ進メテ、霊蛇、… |
27丁ウ |
5 |
5 14丁オ |
 |
| 母ニ進ムル菰羮ヲ奪イ食ツテ… |
31丁オ |
6 |
6 16丁オ |
 |
| 富士ノ郡久左、不孝ノ罰ノ事 |
33丁ウ |
7 |
7 17丁ウ |
 |
| 母ニ蔵シケル海鰻、蛇ト化シテ… |
36丁オ |
8 |
8 19丁ウ |
 |
| 那須ノ伝教、生キナガラ奈落ニ沈ム事 |
41丁オ |
9 |
9 23丁ウ |
 |
| 布鼓 卷之二 (再鞔布鼓巻之二) |
| 老父ノ遥カニ尋ネ来リタルヲ… |
1丁オ |
10 |
10 30丁オ |
 |
| 結城ノ大工町ノ七兵衛、生キナガラ… |
8丁オ |
11 |
14 70丁ウ |
 |
| 河南ノ玄偉、土袋ヲ以テ父母ヲ圧シ… |
19丁オ |
12 |
13 62丁ウ |
 |
| 布鼓 卷之三 (再鞔布鼓巻之三) |
| 不孝ノ娶、狼ニ化スル事 |
1丁オ |
13 |
なし |
 |
| 不孝ノ娶、狼ニ成リテ吾ガ子ヲ… |
12丁オ |
なし |
なし |
 |
| 襄陽ノ杜徽、父ノ歯ヲ打チ欠ク事 |
21丁オ |
なし |
なし |
 |
| 不孝ノ娶、火車ニ載セラルヽ事 |
28丁オ |
なし |
なし |
 |
| 餅ニ小児ノ糞ヲ塗リテ、母ニ進メシ事 |
35丁ウ |
なし |
なし |
 |
| 布鼓 卷之四 (再鞔布鼓巻之四) |
| 孝ト不孝ト、賞罰遁ガレ無キ事 |
1丁オ |
なし |
なし |
 |
| 庠生鄭文献、雷火ニ打タルヽ事 |
15丁ウ |
なし |
なし |
 |
| 娶ト姑 ト中アシキヲ瘳治シケル… |
29丁ウ |
なし |
なし |
 |
| 関羽将軍ノ木像、不孝ノ人ノ首ヲ… |
40丁ウ |
なし |
12 49丁ウ |
 |
| 布鼓 卷之五 (再鞔布鼓巻之五) |
| 宇佐美文七、亡魂ト戦フ事 |
1丁ウ |
なし |
11 36丁オ |
 |
底本におさめられる二十三話のうち、中国の話を翻案したものが八話、あとは日本の話である。勧善懲悪を旨とする因果物語は、そのほとんどが悪因悪果を描くもので、まれに(多くの場合一例)善因善果の物語をおさめることになっているが、『布鼓』では、孝行の乞食源七が、侍に戻った老父に召し抱えられる話(「孝ト不孝ト、賞罰遁レ無キ事」)が、唯一の善因善果物語である。
一番最初の「不孝ノ子ニ贈リシ書」が書かれた経緯について、「布つゞみの序」は、
四十年前、予が童形の友、渡氏なる者あり。此重痾に罹て、父母旦暮に憂惱す。予、時に泉州信田の僧廬に有り。長書を裁して是に投ず。渡氏甚感激して、忽ち不孝を改めて孝子と成る。
と記す。正徳四年(1714)、三十歳の時、白隠は泉州信田の蔭凉寺に掛錫中であった。ここに郷里原宿の本陣、渡辺平左衛門久親からたよりがとどき、子息である渡辺弼英の不行跡を知らせて来た。幼友達でもあった弼英のことを心配した白隠は、これを諌めるために、「不孝ノ子ニ贈リシ書」を書いて送ったのである。
ただし、『布鼓』には、「上巳之日、泉州信田蔭涼蘭若ニ於イテ書ス」とあるのに対して、『諌言記』の末には「正徳四年三月日、京都三条之客舎におゐて書之」とある。両方の記述が正しいならば、三月三日には白隠はまだ泉州にいたが、その後、京都に向かい、三条の旅籠で三月中に、この「不孝ノ子ニ贈リシ書」を書き上げたものということになる。
そして、これより三十三年のちの、延享四年(1747)九月三日、白隠は同じ「不孝ノ子ニ贈リシ書」を浄書して、江戸浅草の村林徳三郎に送っている。『諌言記』はそれの写しである。
この手紙によれば、白隠は延享三年の春、江戸に出て徳三郎の父である恵均老に逢った。その際に、徳三郎のことについて「殊之外、実体成旨、生れつきにて、諸事長しく候ゆへ、皆々も喜悦致され候由」という話を聞いて、安心し喜んでいたのだが、最近になって、恵均老(あるいは他の者)から、息子徳三郎が飲酒の上、不行跡をはたらく旨を知らせて来たので、これを心配し、三十三年前に書いた「不孝ノ子ニ贈リシ書」の物語のことを思い出し、これを清書して送ったのである。
村林恵均がいかなる人物であるかは未詳だが、「恵均老とは師弟同然の挨拶」とあるから、いずれかの師匠のもとでの同参の関係かとも思われる。白隠は延享四年には六十二歳、恵均は「七旬に近き恵均老」とあるように七十歳近いので、白隠の方が年少であろう。
龍吟社版『白隠和尚全集』尺牘の部に「村林是三に与ふ」という書簡が収められている。白隠七十一歳の時の書簡である。その冒頭に、「……貴翁眼病次第に快気の様には被仰越候へとも……」とある。その内容は眼病を治癒するための養生法を説いたものであるが、この村林是三は村林恵均と関わりがありそうである。
さらに、白隠の書いた「無文号」字説の一軸が残る(東京、薮本氏蔵)。これには、
武陵浅草処士、村林四郎兵衛、就予乞法号。予即応之、以無文是三居士之幽称。……
延享第三丁卯暦魁夏仏生日斎後 沙羅双樹下白隠老衲書以授与
とある。これによって、無文是三居士は浅草住の村林四郎兵衛であると分かる。そして、『諌言記』の冒頭には「貴殿事、去年以來、諸事気侭なる身持いたされ候に付、恵均老、并権兵衛殿、四郎兵衛殿夫婦、其外諸親類中、殊之外、気を痛められ…」とあるから、村林四郎兵衛は村林恵均老の親戚のようである。
ところで、この道号記は延享三年四月八日に書かれたものである。『諌言記』には「去春、浅草え参候節、貴殿の噂承り候に」とある。『諌言記』が書かれたのは、その巻末にあるように延享四年(1747)九月三日のことであるから、「去春」は延享三年である。つまり、延享三年の春、白隠は江戸浅草に行ったことになる。
『年譜』によればこの年の秋(七、八、九月)には、甲州の宝林寺に行き、上梓したばかりの『闡提紀聞』を初めて繙いて提唱したことを記すが、江戸行きのことは記録されていない。白隠は甲州に行く前に江戸に滞在していたのである。
さて、本書の『仮名因縁法語』と『布鼓』に収められる物語は、因果応報を説き勧善懲悪を示した、唱導文学作品である。近世に入って、仏教各宗派において展開した仏教文学であるが、白隠の因果物語に先行するものには、次のようなものがある。鈴木正三の『因果物語』寛文元年(1661)、玄瑞の『本朝諸仏霊応記』享保三年(1718)、猷山の『諸仏感応見好書』享保十一年(1726)。以上は曹洞宗の僧によるもの。
また、浄土宗では蓮盛の『善悪因果集』宝永八年(1711、「親ニ不孝ナル者現ニ酬フ事」を含む)、真言宗では如実の『準提菩薩念誦霊験記』寛延二年(1749)、その他、龍正の『勘化一声電』などがある。
また、白隠の時代は、室町時代に始まり、近世になっていよいよ盛んになった怪談文学の発展期でもある。『諸国百物語』延宝五年(1677)、『御伽百物語』宝永三年(1706)、『太平百物語』享保十七年(1732)などが刊行されている。いわゆる『百物語』はこの他にも数多あり、白隠の時代はちょうど『百物語』の完成期にあたる。
白隠の『布鼓』に収められた二十三の話は、単なる怪談ではなく、不孝の行ないによって悪果をこうむることがテーマになっている。不孝の逆である孝行については、すでに室町期から、中国の「二十四孝」の話が翻訳されていたが、近世になって各種の「二十四孝」伝や孝子伝が広く行なわれるようになった。こうした風潮の中で、「孝」ではなく「不孝」という悪業に見られる人間性を描写しようという文学的意図をもって現れたのが、井原西鶴の『本朝二十不孝』(貞享四年、1687)であった。
白隠の『布鼓』は、右のような江戸中期の文学運動の影響を受けつつ書かれたものである。実際に、白隠は先行する作品の物語を翻案収録している。次の二つの例である。
鈴木正三の『因果物語』からは「那須ノ伝教(教伝)」の物語を、そして西鶴の『本朝二十不孝』中から「善悪の二つ車、広島に色狂ひの棒組屋」という話を引き用いている。本書における「那須ノ伝教、生キナガラ奈落ニ沈ム事」(118頁)と「孝ト不孝ト、賞罰遁レ無キ事」(267頁)がそれである。
鈴木正三が描くところの教伝の物語は、わずか150字余(片仮名本『因果物語』)であっさりと書かれているに過ぎない。
下野ノ国那須ノ湯涯、三町隔テテ地獄有リ。那須ノ教伝ト云フ者、山ヘ薪ヲ取リニ行キケルガ、朝飯遅クシテ、伴ニハグルルトテ、母ヲ踏ミ倒ス。サテ山ヘ行クニ。地獄ノ涯ヲ通ル時、俄ニ大地獄ノ出デ来テ、教伝其ノ侭落チ入ル。友達走リ倚テ、頭ヲ取レドモ留ラズ、終ニニエ入リケリ。今ニ至テ教伝地獄ト云ヒ伝ヘテ有リ。教伝甲斐ナシト云ヘバ、俄ニ湧キ出ル也。
『因果物語』ではこの話の直前に、肥前温泉山の「地獄」の話がある(下図参照)。そこに、
地獄涌キ出ル所ヘ指ヲ少シ指入レテ、サノミ熱クナシト云フテ、指ヲ引出シケレバ、彼ノ指熱クシテ叶ハズ。又指ヲ入レレバ熱サ止ム。今ハ快シトテ指ヲ引キケレバ、弥熱サ増シテ堪エ兼ネ、又指ヲ入レ兎角引出サレズ。


というくだりがあるが、白隠はこの部分を取り入れている。つまり、二つの話を合体して新しい物語に翻案しているのである。さらに、正三の『因果物語』では見られないが、白隠は、地獄から戻った伝教に見聞談を語らせている。
また西鶴の「善悪の二つ車、広島に色狂ひの棒組屋」は、およそ1880字であるのに対して、白隠は3000字近くを用いている。字数が多いだけではない。その文学的表現の豊かさにおいて、はるかに前者を上回っているとさえ言ってもよい。元禄文学を代表する井原西鶴を凌ぐなどといえば、いかにも贔屓の引き倒しのように思われようが、決してそうではない。
この物語には善人の源七と悪人の甚七が登場するが、特に甚七の悪玉ぶり、嫌らしさの表現は、この不孝物語の眼目である。たとえば、この甚七がいざり車に僞親父を乗せて初めて乞食に出かける場面は、西鶴の話では、
甚七はかた輪車をつくりて七十にあまる老人を乗て、町筋に出るより涙ぐみ、国を申せば安芸の国、年を申せば廿三、いかなる因果の報にや、ひとりの親を養ひかね面をさらし勧進す、何もお慈悲は御ざらぬか、と声悲しく誠がましく歎きしに、……
とある。ここのところ、『布鼓』では、
甚七ガ父ヲ具シテ町ヘ出ルニハ、町ハズレマデハ、父ヲモ歩マセテ、町ハズレヨリ不定ゲナル面體シテ、ヒコズリモテ、行ク行ク、
「骨フトキ親祖ナレバ、其ノ重キ事土佛ノ如クナン重クテ、腹ノヨハクテ引カルベキ事カワ。哀レ物タビテヨ。物クワネバ、車コソヒカレネ」ト、憎サゲニ哆キ行キニタリケレバ、
「今日ハ不孝ノ順禮ガ來リタルゾ。彼ガ目ノ中ノスヽドサ、物ゴシノ氣ヅヨサ、如何樣ニモ心得ヌ奴ナリ。斯ルヤツハ、透ヲ見テシタヽカニ物偸ムモノナルゾ。久シク門ニナ立タセソ、家ノ内見コマスナ。早ク追イ通スガヨキゾ。……」トテ、更々物與フル人コソナケレ。憎ミ瞋ル聲ノミナン聞コヘニタリケリ。
斯クテ、五丁十町ヒキマワリテ、物少シバカリモロウテ、ヒコズリ返シテ、扨、町ハズレニ成リテ、車引キ留メテ、
「サラバ、老人ヲリ玉ヘ。モハヤ人モ見ヌゾ。アラ辛勞ヤサ、是レカラハ、チト甚七ガノリ申ス。片思ヒニモナラレマイ、此レカラ、ソロソロ引イテヲイキヤレ。ヒバシノ樣ナル痩ズネフンバリ、餓鬼ノダイモチ面白ヤ」ト、引カレテ行ク。(274頁~)
といった調子で、甚七の悪党ぶりが憎々しいまでに表現されているのである。夜になって小屋に帰っての場面、西鶴本では、
甚七、老人に按摩をとらせ終夜蚊をはらわせ、年寄の草臥をゆるさず、眠ば胴骨を踏たたき、腰抜役のおのれめとつらくあたる。
と、あっさりした表現であるが、『布鼓』では、善人源七にネチネチとからむ甚七の悪人ぶりが描き出されている。ねたみそねみの悪口雑言を吐く甚七に、餅をくわせてなだめるが、いうことをきかぬので、源七は酒を買って来て呑ませてやる。
「餠ハ給ブベキガ、己レガ眞似シテ似セ孝行スル事ハ、フツト叶ワヌ事ナルゾ。……」ト、餠ヒキ寄セ、目タヽキセヌ中ニ、グヾト、食イ盡シテ、
「扨、源七ヨ、己レハ町ノ人々ヲ欺キタル習イニ、又此ノ男ヲモ欺カントスルカ。只今、酒呑マサント云イタリケルガ、イデ、其ノ酒呑ムベキゾ。僞リタラ(ン)ニハ堪ユマジキゾ」
トテ、ネメマワセバ、「安キ事ナルゾ」トテ馳セ行キ、酒ヲナン買イ求メテ與ヘニタリケレバ、グト、引キカタゲテ、眞仰ニナリテ、
「祖ヨ、股ツカミ足ヲナンサスリテ得サセヨ。蚊ヲナン追イ出セ」
トテ、七旬ニ近キ老人ヲ、終夜責メ惱マシケレバ……(278頁~)
実に悪党ぶりを描写し得て妙というべきであろう。これほどまでに因業な男ならば、最後に滅多打ちにされ、路傍に棄てられ、狼に喰われて死ぬのも当然ではないか、こう読者を納得させる上で、白隠の筆致はきわめて効果的である。
白隠の筆は、また悪女を語る時にはいっそう冴えわたる。本書にはさまざまな悪女が出るが、大坂久宝寺の櫛屋のずぼら女房が、厚化粧して男あさりに出かける場面など、
己レハ類イモナキ手ヅヽナリケレバ、物ノ端縫一ツスル事サヘ叶ワデ、常ノ業ニハ、ギヤウタマシク髮結タテ、差櫛三四枚、香ガイ六七本、鈿三五本、森ノ如クニサシカザシニタリケレバ、頭ハ左ナガラ著[箸]ノ供養ヲナン見ル如クナリケリ。目口ノ分カチモナクヒヾワレ、欠ケヲツル斗リニ、濃々ト粉脂ヌリコメニタレバ、呉粉モテ彩色シタル炭團ノ如クナン見ヘケリ。斯ク化物ノ如ク恐ロシク粧イ立テ、其ノ上ニケタヽマシク染メ散ラシ、茜裏(セ)シカイドリヒキカケテ、是レ見ヨト云ワヌ斗リニ、外面ニソボロ立チテ、片臂ハリ、立臼ノ如クナル腰、少シタワメ、夜着ノ袖口程ナル口ツボツボメテ、首打チ傾ゲ目ヲナンヒキホソメ、上目蓋押シ下ゲ、佛貌シテ、如何ニモ物思イ姿ニテ、殊勝ゲニヒサシノ柱ニヨリソイ、往來ノ人ヲ見カヘリ見ヲクリニタルハ、左ナガラ實モナキ婬レメノ追イ枯シタルニ露タガワザリケルハ、如何サマ奇異ノ曲者ニゾ見ヘケル。(240頁~)
さながら「跛鼈、眉を払って晩風に立つ(跛のスッポンが化粧して夕涼み)」ともいうべき光景は、ぞっとするばかりではある。「娶ト姑ト中アシキヲ瘳治シケル老医ノ事」で描かれる、嫁と姑のいがみあいの場面など、まさに圧巻というべきである。
姑ハ娶ヲ憎ミ嫌ヘバ、娶ハ姑ヲ瞋リ恨ム。サテ、是レカラガ龍虎ノ爭ヒ。姑ハサナガラ澁染ノ越後縮デ上鞔仕タル皺斗リナル貌ヲ瞋ラシ、白毛ハ倒シ(マ)ニヨレ上ツテ、拂子ヲ豎テタル如クナルガ、田光ノ樣ナル眼ヲ見張リ、齦斗リデ齒咬ミヲナシ、左ナガラ角ノナキ鬼トヤ人ノ云フベキ。
朝ハ持佛ニ向フト思ヘバ、帚ヲツトリ、妄執ノ雲ノ塵掃キカケテネメ廻リ、晝ハ茶本ヘ呼ベドモ來ラデ、桶鉢チ投ゲテネメ廻リ、暮レニハ娶ガ夕餉ノ邪魔シテ、火ノ坪ニ水打チカケテ、火箸ヲイロリニ突キ立テ立テネメマワリ、今マデ此ニ在ルヨト見ヘシガ、背戸亦門ニ眼ヲ賦ツテネメマワリ、又或ル時ハ、織女ノ夕機立ツル窓ヲ望イテ、娶ガ噂ノ管卷絲繰リ、腰ニハ梓ノ弓ヲ張リ、額ニ四海ノ浪風吹キ立テナリワメケバ、娶女モ一期ノ大事ナレバ、ヨハミヲ見セジト、臂張リ目ヲハリ氣ヲハツテ、「物物シ、アノ婆女ガ鳴ルト云ヘドモ、左ゾ在ルラン。破レカブレト出ルナラバ、姑ナリトモ微塵ニ爲サン」ト、メノトヽ夫トヲ小ダテニトツテ、火出ル斗リ、スリ合イケル勢イハ、妖疫神モ面ヲムクベキ樣ゾナキ。(321頁~)
家庭というせまい舞台での、女どうしの陰険な心理戦、その鍔迫り合いのさまは、現代人の我らをも唸らしめる筆致であろう。
また「不孝ノ娶、狼ニ化スル事」には、『伊勢物語』を下敷きにした表現が見られるし、その他、随処に見られる、五七の「道行調」の表現は、きわめて効果的で、江戸時代の読者は知らず識らずのうちに、浄瑠璃の語りを聞いているような臨場感を味わったことであろう。
ここには、ありとあらゆる犯罪がある。傷害、傷害致死、親殺し、子殺し、虐待等々。そして、その結果として、自殺、非業の死、あるいは発狂し、廃人となる者など。この、おどろおどろしい因果物語は、四半世紀まえのものではあるが、古くさいなどと容易の看をしてはなるまい。人間の営みはさして変わってはいないのだ。毎日のニュースで報じられ、ワイド・ショーで繰り広げられる因業絵巻は、さながら、現代版因果物語であろう。白隠はこうした、まがまがしい「事件」を見事に描写して、読者に人間心理の暗部を提示し、見せつけるのである。
松蔭寺のすぐ近くに植松家という豪家があった。四、五代の当主は禅師に私淑した人である。その六代目与右衛門季英が残した『せ間見聞覚』という記録がある。明和四年~明和九年、原宿およびその周辺で起きた事件など、当時の社会世相を記したものである。季英は一七二九年生まれだから、禅師より四十四歳下。記録は禅師最晩年、多くは禅師遷化の後のものだが、社会世相は禅師の生前とさほど相違はあるまい。当時の世情を伝える記事を拾ってみると次のようである。
明和七年。「隣宿元吉原の渡辺彦左衛門のせがれ佐平太(三十六、七歳)は、三、四年前、博奕で負けた金の穴埋めに、三十両もする日蓮上人の直筆を八両で売り飛ばした。親から勘当され、今では裸に蓑を着て、あちこちで金を無心し歩いている」。
「小田切新五郎様(役人)手代の山路幸八(六十三歳)という人が、このごろ吉原宿和田屋の飯盛女を何人も引き連れ、修善寺に入湯にいった。これまでに関係した女は七百人という。この八月、東海道松並木の土手工事費の一割を横領した咎で捕まり、江戸に送られ、十二月、打ち首になったという」。
「五月十九日、蓼原源流寺の庫裏婆(四十七歳)が寺男(三十三歳)と心中。男が一緒に出奔しようと口説いたが、女がきき入れぬので、無理心中に及んだとのこと」。
この源流(立)寺は、かつて白隠の弟子快龍が住職した寺だが、この時の住職は誰であるか不明。この時から三十四年前に、白隠はここで法華経を講じたことがあった。
「田中村の喜平次方に一、二年前から居候していた今太夫という義太夫の太夫、この五月、喜平次の娘と駆け落ちをした。ところが、その母親も太夫と懇ろの関係で、後を追って出奔した」。
「十一月二十七日、東原の小右衞門(三十六、七歳)という名主が行方をくらました。三百両を使い込み、これを持って逃げた。手をつけた女が原村に八人あり、二人は腹が大きい。沼津にも女が一人あり、また新玉屋のイチノという飯盛女も買ったという。原近在三十ケ村にこれほど淫乱な者はない」。
明和八年。「元吉原の多右衛門、若い時分には、吉原宿の大黒屋で奉公し、次第に成功し、高も七、八十石になり、御用金を納めるほどになった。それに、仏信心に熱心で、白隠和尚の月例の催しにも参加するような人だった。せがれは二人あり、家は兄に嗣がせ弟には分家出して油屋をさせている。ところが、この二人の息子、親の存命中から、博奕など悪いことに手を染め、すっかり身持ちが悪くなってしまった」。
とりたてて非道い話ばかり選んだというわけでもない。こんな泥沼のような世相を禅師はよくよく熟知しておられたことであろう。仏法は、泥中の蓮花であるという。衆生済度のためには、その花の色香の研究ばかりでなく、また泥沼も熟知しておかねばならないのである。
白隠は『延命十句観音経霊験記』で、ひとたび死んだ者が、観音経の功徳によって蘇生し、あるいは地獄で見聞したことを語る、といった奇話をいくつか書き、そして最後になって、それらの物語は「正眼に見来れば、唯是世間住相、有為夢幻、空華の談論、取るに足らず」と、一転して否定し、真の大霊験は見性することであるとしている。そのような白隠禅師の本分からすれば、本書のごとき因果物語も、これまた「空華の談論」、絵空事の方便に他ならないのである。
革のかわりに布をはった鼓は音が出ない。その布鼓を書名にしたのも、この空華の方便を言ったものであろう。そして、鳴らぬ鼓の響き「布鼓の秘調」が耳に入るならば、必ず思い当たることがあろう、と白隠は勧めるのである。
白隠遷化から二十年のち、天明八年(1788)に刊行された『諸国業報因縁集』巻之五に、次の話がのる。
宝暦年中の事なりしが、駿州原の駅の在の百姓何某、二十二三なるが、父の死後、母に大不孝也。宝暦十一年七月十二日の夜、「明朝未明に、草刈に行程に、食事を早く拵置かれよ」といふ。母は夜深る迄多用にて、其営なかりき。息子甚憤り、「暮には帰るべし。早く食事用意」と言ふて出ぬ。されども母は、聖霊祭り旁事多く、食事の営遅くなりぬ。息子帰りて大に恚り、母が飾置し聖霊棚の備物位牌迄引出し、蹴散し雑言す。母は彼が常の病又起りしと不便に思ひ、又棚を飾り置れたり。其夜更て後戸外に泣叫声あり。母驚て息子を見るに見へず。戸外に二鬼有つて息子を訶責す。母、裏道より隣家の者を呼制すれ共力及ばず。東雲の比手足も舌もぬかれて死す。怖しき事なり。白隠和尚会座にて大衆に語り申さる。
これは、本書に出る宇佐美文七の物語である。これに見るように、白隠の因果物語は刊本以外でも、語り伝えられていたようである。
本書は、白隠仮名法語の中で、もっとも文学性の高いものといってよい。しかしながら、仏教文学としてはほとんど無名のままで埋もれてしまっているのはどうしたわけであろうか。井原西鶴はともかく、鈴木正三の『因果物語』は、国語・国文学の立場からかなり研究されており、岩波文庫の『江戸怪談集』に収められ、普及もしている。これに対して、『布鼓』はほとんど等閑視されたままである。国文学の分野からの参入も、大いに期待したいところである。