一瓢因甚、欲捺鮎魚。 (一瓢もて
江湖水闊、道術有余。 (江湖水は
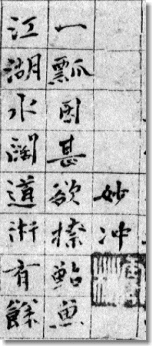 雲林妙冲(生没年不詳)、仏光派。「江湖水闊、道術有余」は、『淮南子』俶真訓に「魚相忘於江湖、人相忘於道術(魚は江湖に相い忘れ、人は道術に相い忘る)」とあるのをふまえる(16)。
雲林妙冲(生没年不詳)、仏光派。「江湖水闊、道術有余」は、『淮南子』俶真訓に「魚相忘於江湖、人相忘於道術(魚は江湖に相い忘れ、人は道術に相い忘る)」とあるのをふまえる(16)。
ここでは敢えて「魚」字を使わず「江湖」と「道術」だけを用いているが、そのことによってナマズと同じ「魚」を含んだ成句を想起させるところに、この詩の妙味があるといえよう。
ここにいう「道術」は仙道の術のことではない。「魚相忘於江湖、人相忘於道術」は、魚は川や湖の水の中にいてしかもそれを忘れているが、そのように、人は道の世界にいてそれを忘れている、という意味である。
「道術有余」の訳は、福嶋氏は「やりようは幾らでも」、『禅林画賛』では「その道を心得た者はいくらでもいる」とし、島尾氏はその解釈を拡大し「鮎をおさえる道術」「妙手や使い手はいくらでもあるだろう」としているが、いずれも非である。
本拠である『荘子』内篇、大宗師にはつぎのようにいう(17)。
子貢曰く「然らば則ち夫子は、何の方にか之れ依る」。曰く「丘は天の戮民なり。然りと雖も、吾れ汝と之を共にす」。子貢曰く「敢えて其の方を問う」。孔子曰く「魚は水に相い『荘子』にいう「道術」も、仙道の術や道を得るための何らかの具体的方術をいうのではない。「無為自然の道を体得していて、その道の中にあって生きる」ことである。造 き、人は道に相い造 く。水に相い造 くる者は、池を穿ちて養 は給 り、道に相い造くる者は、事無くして生 は定まる。故に曰う、魚は江湖に相い忘れ、人は道術に相い忘る」。
「道術有余」の解釈は瓢鮎図解釈において、極めて重要な語である。右の『荘子』大宗師の一段を福永光司訳(18)で見てみよう。
いったい、魚は水があってこそ真の魚と成ることのできるものだが、それと同じく、人間も道によってこそ真の人間と成ることができるのだ。福永訳の「人間は万物斉同の実在世界そのもののなかに一切の人間的なるものを忘れ去る」が「道術相忘」にあたる。また近年では、「道術」の「術」には意味がなく、「江湖」とあわせるために二字にしただけであるという説もある(19)。
また、魚は水によってこそ真の魚となるから池を掘ってそのなかに放ってやれば、十分生育してゆくことができるが、それと同じく、道によって真の自己となる人間は、道の自然に従って人為を捨て、思うことなく為すことなく、ただ与えられた現在を与えられた現在として生きてゆけば、そこにこそ真に充ち足りた人生が得られるのだ。
「魚は江湖に相い忘れ、人は道術に相い忘る」という言葉があるが、魚は広々とした湖や江 のなかで真の解放を楽しみ、人間は万物斉同の実在世界そのもののなかに一切の人間的なるものを忘れ去ることによって、とらわれなき生の自由を逍遙することができるのだ。
『荘子』外篇、秋水には「濠梁上の問答」といわれる一段がある。
荘子はあるとき恵子とともに濠水に遊んだ。のんびりと川の中を泳ぎまわっている魚を見た荘子が「これこそ魚の楽しみである」というと、恵子が、「魚でないのにどうして魚の楽しみを知ることができるのか」と質問し、以下、実在と認識をテーマに問答がつづくものである(20)。
浮山法遠禅師(991〜1067)は、この一段を引いた上で、次のように述べている(21)。
魚は水を以て命と為す。水を見れば即ち魚を見る。浮山法遠によれば、「魚相忘於江湖、人相忘於道術」は「天地一指、万物一馬」であり「一即一切、一切即一」なのである。所謂 る色心不二、彼我無差なり。其れ或 し岸を離れて水を見ば、則ち水の外に別に岸有り、水・岸既に二法を立せば迭 いに失う。魚水各おの異なれば、乃ち天の経 を乱 り、物の情に逆 う。其れ或 し情に逆 わず、経 を乱 らず、均しく天和に順ずれば、「魚相忘於江湖、人相忘於道術(魚は江湖に相い忘じ、人は道術に相い忘ず)」(というごとく)、岸を見ば即ち水、水を見ば即ち魚、天地一指、万物一馬、空は実相に同じ、一体にして諸 無し。水を待たずして水、岸を待たずして岸、魚を待たずして魚、然る後に魚水を知る。首楞厳経に曰く「如来蔵中の性水は真空、性空の真水は清浄本然にして、法界に周徧し、衆生の心に随い、所知の量に応ず」と。又た曰く「一毫端に宝王刹を現ず」と、豈に惟だ魚水のみならんや。又た経に曰く「一即一切、一切即一、異相無く別相無く、前後際断す」と、此の如くならば、処として魚ならざるは無く、処として水ならざるは無し。豈に濠梁の上に游ぶを待って、然る後に魚水を知らんや。
また、この「江湖」の語は禅林では、雲水修行者のための世界という意味も持っている。無著道忠の『禅林象器箋』第五巻、称呼類上「江湖」に次のようにいう(22)、
『荘子』大宗師に云く、「泉涸れて魚相いつまり大修館の『禅学大辞典』「江湖」で「馬祖道一は江西に住み、石頭は湖南に住し、天下の禅僧がこの二師のもとへ往来云々」とするのは誤りである。與 に陸に処り、相呴 するに湿を以てし、相濡おすに沫を以てす。如かじ、江湖に相忘せんには」。忠曰く、江湖は二水の名なり。
今(『虚堂録犂耕』では凡に作る:芳澤補)、江湖と言うは、江外湖辺は本と是れ隠淪の士の処する所。
『蓮社高賢傳』に周続之が〈心、魏闕に馳せる者は江湖を以て桎梏と為す(情、両忘を致す者は市朝も亦た巌穴なるのみ:『虚堂録犂耕』によって、芳澤補)〉と曰い、「駱賓王が序」に〈廊廟と江湖と致を斉しくす〉と曰い、「范希文が記」に〈既にして星象を動かして江湖に帰る〉と曰うが如き是なり。
故に禅士の名山大刹の外、江上湖辺に散処するを、此を江湖の人と為す。或いは出世して名山大刹の住持と為らざる者、聚会して一処に在る、亦た江湖の衆と為す。
然るに相い伝えて江西の馬祖、湖南の石頭、往来憧々というを以て解と為す。此の説、学家の肺腸に浸染して、浣濯す可きこと難し。
此方の禅林の江湖の疏に名を題して〈平沙某〉〈遠浦某〉等と曰う。亦た粗 ぼ其の字義を知るに足れり。『伝灯録』石頭の章に「江西は大寂を主とし、湖南は石頭を主とし、往来憧憧として並びに二大士の門に湊ると〉。則ち二祖師の法席盛昌なり。今の隠淪の義に非ず。
上で、無著道忠は「この誤解がしみついて抜けないでいる」と嘆いているが、現代までその弊は続いているのである。
江湖は隠淪の士、すなわち修道者の居る場所である。そして無著道忠も『荘子』の「魚相忘於江湖」を引いているように、江湖(天下・世界)はつねに「魚相忘於江湖」との関連で用いられて来たこと、次の例にも見るとおりである。『松山集』「灘隠説」に(23)、
涒弟記室、自ら灘隠と号し、予に其の意を説かんことを請う。予曰く、棘津に魚なる者有り、初め人の好音を懐く無し。而して周文の祥夢有り。釣竿を持ってはいるが、糸も餌も
……桐江に亦た魚なる者有り。復た人の一顧を寄する無し。而して光武の久要不忘にして招く有り。
……信都に賢弟の徒有り、手に竹を持つ。其の竹、緡 せず餌釣 せず。江湖の上に寂寞として道術を相忘る。詒々然たり洋々乎たり。我なるか魚なるかを知らず。……
いま、この賛詩三における「江湖」も単なる魚(鮎)の住処というだけでなく、同時にまた禅道修行者の居るべき世界をも併せ含意している。
「江湖水闊、道術有余」の語は「一心法界」と言ってもよい。浮山ふうにいえば「天地一指、万物一馬」であり「一即一切、一切即一」という世界観である。
宇宙そのもの、山河大地、一木一草、男も瓢箪も鮎も、ことごとく仏性(仏心)ならざるはない、そのただ中にあるのに、どうしてまた心(瓢箪)をもって心(鮎)を求めようとするのか。
瓢鮎図の背景にある茫漠とした山とその向こうにある空、これが「江湖」である。空と地と水とが混然一体となって描かれているところは、まさに一心一切法の世界を開示したものであろう。
【訳】どうして(あえて事を生じさせ)、瓢箪で鮎をおさえようとするのか。
魚は意識せずしてどっぷり広濶な水中につかっている。
そのように人もまた無限の
初出『禅文化研究所紀要 第26号』(禅文化研究所、2002年)