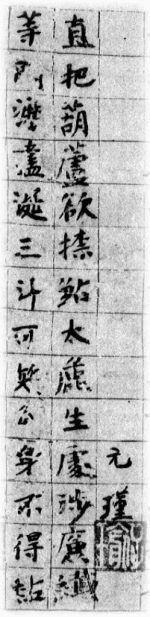
直把葫蘆欲捺鮎、
(直に葫蘆を把って鮎を
太麁生処渉廉繊。
(
等閑瀝盡涎三斗、
(
可笑終身不得黏。
(笑う可し、身を終うるまで得ずして
子瑜元瑾(生没年不詳)、大覚派。建仁寺住。
「太麁生」は「はなはだ荒っぽい」。「渉廉繊」は、『虚堂録犂耕』(66)に無著道忠いわく「心、微細に渉って造作するなり」。荒っぽいようでいて、なかなか繊細。
「等閑」は『虚堂録犂耕』では「疎略、尋常」とするが、ここではその意では必ずしも通じない。『禅林画賛』では「徒らに」と訳しているが、なお未穏。「等閑」ははなはだ広い意味をもつ言葉である。ここでは「ゆくりなく」と
「涎三斗」、『禅林画賛』注に「たくさんのよだれ。作者元瑾の念頭には、杜甫『飲中八僊歌』の〈汝陽は三斗にして始めて天に朝す。道に麯車に逢へば口は涎を流す〉があったと思われる」とするのは非である。
杜甫は「酒三斗」を言っているのである。訳には「だが徒らに三斗もの涎を流し尽くすだけで、それで鮎をへばりつけようにも一生叶わぬとは笑止の沙汰」とあるから、男が(酒を想像しながら)涎を垂れ流してそのネバネバで鮎をくっつける、ということのようであるが、かかるナンセンス・ギャグはこの詩画軸にふさわしくはない。
冒頭の大岳周崇の序に「無鱗多涎之鮎魚」とあったように、涎はヨダレではなく魚の表面の粘液の義と解するのが自然だろう。ナメクジの這った跡を蝸涎というごとし。
「可笑終身不得黏」、「黏」には「ねばりつける」意があるが、男が自分の涎でくっつけることが不自然であることは上に見た。あるいは、鮎の粘液を利用して瓢箪にくっつけるとも解せるが、全体の意が通じない。よって「身を終うるまで得ずして
【訳】瓢箪でいきなり鮎をおさえようとは、はなはだ荒っぽい手口だが、きめ細やかな気配りもそこにはある。
だが(鮎は)不意にネバネバを流す。結局、捉えられず、(鮎が)いつまでもネバネバとはお笑いだ。