【第3回】 渡唐天神図について

■渡唐天神図 (Flash)
「渡唐(宋)天神」とは、詩禅一致を目指す五山僧によって、1400年前後に創作された話で、日本の詩神である菅原道真が、夢の中で径山の無準禅師に参じて、一夜にして印可を得、梅一枝をもって帰った、というものである。五山以降、禅林では多くの渡唐天神図が描かれ、また、詩にうたわれて来ている。
菅原道真(845~903)が無準禅師(1178~1249)に参じたというのである。死没年で計算して、三百四十六年も前の人間が今の世に戻って来て参禅したということになる。歴史事実としてあり得ないことである。あまりにも荒唐無稽な話であるから、禅僧でさえも、そのようなことはあり得ないと批判する者があったほどであるが、このような話が創作されたのには理由があったのである。
「渡唐天神」説話成立を証すもっとも初期の文献のひとつに、花山院長親の『両聖記』(『群書類従』巻十九)というものがある。両聖とは無準師範と北野天神である。この書はいわば「渡唐天神マニフェスト」ともいうべきもので、なぜこのような話があり得るのかが、仏教の立場から闡明に述べられている(句読点、私に補った)。
此事、やまともろこしの伝記にかきのせぬ事なるを、をろかなる身のあさき心にては、さること有べしとさだめむ事、はばかりおほし。又このことはり、すべて有べからずといはむ事、その咎をまねきぬべし。……凡情にておしはからば、かたがたにつけて、うたがひありぬべき事ぞかし。しかはあれど一心法界に遠近のへだてなし。千万劫の転変又即今のうちをいでず。
普通の人間の常識(をろかなる身のあさき心=凡情)で考えるならば、あり得ないことだが、一心法界という仏教の立場からするならば、時間や空間を超越して存在するのが真如なのだから、三百五十年前が今で、中国が日本であっても、いっこうに差し支えはない。
歴史的事実としては「無」であるが、過・現・未を通貫する仏理の立場から言うならば「有」であるというのである。十方三世はただ一心に帰するのであるから、遠近の隔てもなく、千万年以前が即今となるのである。『両聖記』はさらにいう、
抑、天下のことはり、有無のふたつをいでず。有と云よりみれば、古あり今あり、我あり人あり。…無といふにつきてみれば。仏なし衆生なし。天地日月、山川草木もみな是幻化なり。九流百家、四韋五明、色々様々にかきをき、言伝へたる事、たゞ名字のみ有て実体なし。
『遠羅天釜』は白隠の代表作のひとつであるが、これに弟子の斯経が書いた「客の難ずるに答う」という文が添えられている。白隠の言わんとするところを簡明に解説したものであるが、そこに、
大毘盧舍那…ノ本体ハ、猶ホ清浄ノ摩尼宝珠ノ如シ。而モ能ク種種ノ色像ヲ現ズ。…総ニ是レ所現ノ物ナリ。無現ニシテ現ナルガ故ニ無ニ非ズ。現ト雖モ不現、又タ有ニ非ズ。
とある。仏智そのものの本質(大毘盧舍那仏)は一切のすがた形を離れている。けれども、現実世界の存在がどのようなすがた形で現われ出ても、それをことごとく映し出す。一切の存在はこれらの現象として現われる。本来色相を絶しているのだが、現象として現われるのだから無というのでもない。現象として現われるけれども、その本質は色相を超絶しているのだから有でもない。それが仏智であり、一心法界の真如だというのである。
ところで、白隠の渡唐天神像の賛には、
唐衣おらで北野の神ぞとは
そでにもちたる梅にても知れ

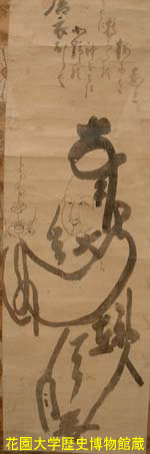
とある。この歌が生まれた事情について、『菅神入宋授衣記』(『群書類従』巻十九)に次のように記す(原漢文)。
一朝、天未だ明けざるに、丈室の庭上に一叢の茆草の有るを見る。(無準)禅師、自ら謂えらく「昨の夕、此の草無し。今の旦、甚麼と為てか、之を生ずるや」。時に神人有り、隻手に一枝の梅花を擎げて、突然出来たる。禅師問うて曰く「汝は是れ何人なるか」。神人無語。唯だ庭上の茆草を指す。禅師、忽ち謂って曰く「茆草は菅なり」と。即ち扶桑なる菅姓の神なることを知る。神人、一枝の梅を禅師の前に呈す。胡跪して、一首の和歌有り。曰く、
唐衣不織而北野之神也、袖爾為持梅一枝。
「唐衣」とは、天神の着けた中国風の道服のことであるが、また「袖」にかかる詞でもある。「おらで」は「不織」あるいはまた「不折」、すなわち「織らざる衣」あるいは「折らざる折枝」の意を含む。
天野信景(1663~1733)の『塩尻』巻七三には、五山文芸を代表する希世霊彦(1404~89)の渡唐天神画賛のことが記されており、次の和歌を載せる。
唐ころも をらぬ袂も にほひけり
あふくに高き 梅の春かせ
「織らぬ衣」である。日本には古くから「天の羽衣」伝説がある。あの天女が身にまとう羽衣は無縫である。「天衣無縫」という語もある。いわゆる不織布や、現代でいうシームレスということではない。縫い目がないとは、人工のまったく加わらぬ、天性そのままのということである。経典には「無縷不織衣」というものもある。いずれも天神・天女の召し物であって、現実のこの世にはあり得ぬものである。では、無いのかというと、そうではない。有にして無、無にして有なるものである。
白隠の渡唐天神図で、天神が着ているのはそもそも何なのか。もう一度、観察してみよう。
それはさながら衣のように描かれてはいるが、衣ではない。つまり、絹で織られた布でできた衣ではない。天神は「南無天満大自在天神」という名号を着ているのである。愚極礼才(1370~1452)は『天満大自在天神宝号記』(永享6年、1434)の中で、この七字の宝号は「諸仏の心体、衆生の妙用」を表わすもので「人々の自性の名詮」であると言っている。仏心であり、本有の自性、人々の中にもとからそなわっていて、変幻自在にはたらく「こころ」、それが「織らぬ唐衣」である。
『遠羅天釜』(巻之下)で白隠はいう、「有ト云ワントスレバ有ニ非ズ、無ト云ントスレバ無ニ非ズ」、形に見えず、言葉に表現できない、それでいて自在にはたらいている「人々具足ノ妙法ノ心性」(巻之下)を見届けよ、と。このような趣旨を説いた自分の著作に、白隠は渡唐天神の和歌「唐衣おらで北野の神ぞとは……」から、「おらで」を採って『遠羅天釜』と命名したのである。有にも非ず無にも非ざる本具の自性、これが「織らざる衣」であり「折らざる折枝」である。
白隠の『遠羅天釜』は、これまで、すべての辞書や書物において「おらてがま」と呼ばれているが、上の趣旨を理解しない、不注意な誤りというべきであろう。白隠自身も「オラデガマ」と濁音で読ませている。
人丸像も、渡唐天神像も、白隠においては同じ意味を持っているのであるが、そのことを整理して見よう。
柿本人麻呂も菅原道真も、ともに日本の学問・文学の神として、古くから尊崇されて来た存在である。人丸は、火伏・安産の神にもなり、他方天神は江戸期になると寺子屋の本尊になり、天神経とともに庶民の信仰をあつめた。
人丸像も天神像も、その身に着けているのは衣ではない。人丸は「ほのぼの……」という和歌を着ている。両神ともに、和歌あるいは名号という文字を身につけているのだが、その文字にいうところは、日本の精神、日本のこころ、ともいうべきものである。
身につけているというよりは、その心そのものが身体に他ならない、つまり、両神が「日本の心」を体(本質)としていることを表現しようとしているのである。
室町の時代に、渡唐天神のような話がなぜ創作されたのか。そのひとつの理由は、禅僧たちが、既に先行して存在した北野天神信仰を禅に取り入れようとしたことであろう。日本を代表する学問(文学)神である菅公が、中国伝来の思想である禅に参じたという形をとることによって、外来思想である禅を日本に普及させ根づかせ、日本化させようという意図があったと思われる。
かかる奇蹟話は、実は、北野天神ばかりではない。日本の最高神である伊勢神宮の天照大神が参禅したという話すらある。聖一派と法灯派の二つの流れを受ける別峰大殊(1321~1402)は、天照大神から藕糸の袈裟を授かり、さらに天照大神の自画自賛像(!)を授かったという。そのような画像は、もちろん神によってではなく、誰かの手によって作成されたのだが、今もなお岡山の松林寺に現存している。
また、伊勢の大空玄虎(1428~1505)には天照大神が入室参禅した、という説話もある。白隠は皇大神が別峰に与えたという自賛自画像を岡山で実見しており、その経緯を『仮名葎』で取り上げている。
渡唐天神説話の誕生と同じ時期であり、禅を日本化させ定着させていく過程で創出された奇蹟説話である。神さまの自画自賛像などというと、聡明な現代人からは、埒もないと一笑に付されようが、先に見たように、一心法界の立場からすれば、いかなる奇蹟説話もいっこう奇蹟ではないことになるのであって、エホバやアラーが参禅しても不思議ではないということにもなるわけである。
ところで、白隠禅師は、貞享二年乙丑の十二月二十五日夜丑の刻(丑年丑月丑日丑刻)に生まれた(『年譜草稿』『壁生草』)。この因縁は白隠の天神信仰の原点ともなっている。
白隠は天神の再来であり、渡唐天神に他ならない。
外国の文字である漢文による詩文の作成を至上としたのが五山文学の時代であった。白隠ももちろん多くの漢文著作を表わしているが、何といってもその特徴は、日本語である仮名法語を多く書き表わし、また、民衆が熟知している当代の俗謡などを賛に付した禅画を多く描いて禅の立場を表明し、これによって民衆を教化し、禅の日本化に努めたことである。そのような意味で、白隠は江戸の時代にふさわしく、装いあらたに生まれかわった「渡唐天神」であったと言ってよい。
天神の再来であることは、白隠においても意識的に自覚されていたのである。白隠は衆生済度の教化のために、お多福女郎やお婆々など、さまざまな人物を描くが、その着物には梅鉢の紋がつけられていることが多い。梅鉢は天神の紋である。天神の再来たる白隠の分身であるぞよ、というトレード・マークでもある(拙稿「お多福美人のこと」、『禅文化』167号)。
姿かたちのない白隠のこころが、自由自在にあらゆる人物に変化し説法するのである。その白隠が見届けよとすすめる「有にも非ず無にも非ざる本具の自性」、そのための方便が「隻手の音声」である。『隻手音声』で白隠はこう述べる。
いま、両手を合せて打てば、パンと音がするが、ただ片手だけをあげたのでは、何の音もしない。『中庸』に「上天の載は声も無く臭も無し」というのは、ここの消息をいう。また、謡曲『山姥』に「一洞空しき谷の声、梢に響く山彦の、無声音を聞く便りとなり、声に響かぬ谷もがな」というのも、ここの秘要を言い表わしているのである、と。
人丸像と天神像にまとわせた「織らざる衣」は、見ることも聞くこともできず、姿かたちにあらわせぬ、それでいて、確かに在る「こころ」、本有の自性のありようを表わしているのである。
初出『季刊 禅文化 188号』(禅文化研究所、2003年)
|