石人水上捺葫蘆、 (石人、水上に葫蘆を
一捺鮎魚捺又無。 (鮎魚を
捺不得時重捺着、 (捺え得ざる時、重ねて
觸飜手中珠。 (触れれば
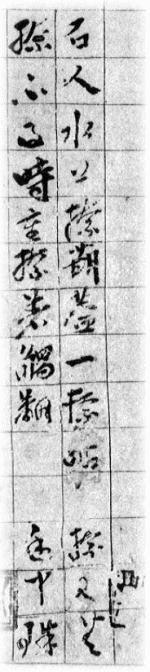
この賛詩では賛者の署名がなく落款だけが黒印で捺されている。始めから署名がなかったことは考えられないので、おそらくは修復の際に剥落部分が既に失われていたものであろう。
『禅林画賛』で「石人」を「無知の石人」、島尾氏が「無知の男」と訳するのは当たらない。
石人は木人や石女などと同じように無情物をいうのであり、知・無知という相対を超えたところであって、「無知(おろか)」という世上の概念を含まぬ存在である。禅録では機語によく用いられる。『五灯会元』第六、洛浦元安禅師章に、
直に須らく旨外に宗を明らむべし、言中に向かって則を取ること莫かれ。是の以 に、石人、機、汝に似たらば、也た巴歌を唱うることを解 くせん、汝若し石人に似たらば、雪曲も也た応和すべし(石人也機似、也汝解唱巴歌、汝若似石人、雪曲也応和)。
巴歌は低俗な田舎歌。雪曲は白雪曲、誰も解する者のないような向上の曲調をいう。石人の機(はたらき)にして初めて、至難の曲調に和することができるということである。
この「石人機似汝、也解唱巴歌、汝若似石、雪曲也応和」の語は『碧巌録』第九六則、第二頌の評唱に引かれているが、そこでは洞山守初の、
「五台山上、雲もて飯を蒸す、古仏堂前、狗 、天に尿 す。刹竿頭上、縡子 を煎る、三箇の胡孫 、夜、簸銭 をす(五台山上雲蒸飯、古仏堂前狗尿天。刹竿頭上煎縡子、三箇胡孫夜簸銭)」、
杜順和尚の、
「懐州の牛、禾 を喫 えば、益州の馬が腹脹 るる、天下に医人を覓 めて豬 の左膊上に灸をす(懐州牛喫禾益州馬腹脹、天下覓医人灸豬左膊上)」、
それに
「空手にして鋤頭 を把り、歩行して水牛に騎る、人、橋上より過ぐれば、橋は流れて水は流れず(空手把鋤頭歩行騎水牛、人従橋上過橋流水不流)」
といった代表的な機語とともに並べられている。いずれも情識を絶した神通妙用をいう語である。また、『五灯会元』第十五、長楽山政禅師章には次のようにある。
僧問う「祖師の心印、何人か提掇す」。師曰く「石人妙手在り」。曰く「学人還 た分有りや也た無 や」。師曰く「木人、整不斉」
ここでは「祖師心印」という問いに対して「石人妙手在」と答えているところに注目したい。右の例と同じようにここでも、石人は分別情識を絶した機用、妙用をもつ存在である。
いま、ここの詩一九においても、おさえようとしている鮎が「祖師心印」の象徴であって初めて、「石人」の語が意味をもちえることになる。無情物である石人にこそ妙手があって祖師の心印を提掇し得るというのである。「妙手」の語は【第24回】にも出るが、いまここでも石人は「妙手を持った石人」という含みで用いられている。「無知の男」ではない。
「一捺鮎魚捺又無」、「又」字、未穏在であるが、古謄複本に従っておく。「触飜□□手中珠」は、「貪観天上月、失却手中珠」(62) の句をふまえたものであろう。外にのみ求めて、自己の内なる宝(仏性)を見失うことである。
したがって□□は「失却」とし、「触飜失却手中珠(触れれば飜って手中の珠を失却せん)」としてよいであろう。「手中珠」は自家の珍宝、自己の内なる仏性の譬喩である。外に向かって求め、触れたと思ったら、もはやそれは宝ではない。つかまえたと思ったら、もはやそれは心ではないのである。【第9回】詩九の作者である西胤俊承の「七処徴心」頌にいう(63)。
七処徴心心底物、(七処徴心、心、底物 ぞ)
阿難当時枉受屈。(阿難当時 枉 に屈を受く)
直饒指出得分明、(直饒 い指出して分明なることを得るも)
也是獼猴探水月。(也た是れ獼猴 の水月を探るがごとし)
七処徴心のことは前に見たとおりである。三、四句は「もし、これが心だとはっきり指し示すことができたとしても、それは猿が水に映った月影をほんとうの月だと思って水をすくうようなもの」ということである。すなわち「触れれば飜って手中の珠を失却」することと同じ趣旨をいう。
【訳】石人が(妙手をもって)水中に葫蘆をおさえて鮎をつかまえようとする。
一おさえ、さてつかまえたかどうか。つかまえられずにまたおさえる。
(鮎が心印だと思って)外に向かって求め、それに触れるならば、かえって自家の宝(自家の仏性)を見失うことになろう。