孟八郎漢是掠虚操瓢□走趁□魚
粘滑瓢宛轉東撲西捺□□□□□
唯拈竹竿持揺頭
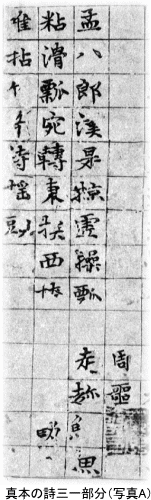
厳中周噩(1359~1428)、夢窓派。等持寺、相国寺、天龍寺、南禅寺住。
この詩は、断句がはなはだ困難である。これまでの断句および訓読の例をみる。まず福嶋俊翁氏の場合、
[1]孟八郎漢是掠虚。(孟八郎漢是れ掠虚)
[2]操瓢□走趁鮎魚。(瓢を操って□走鮎魚を趁ふ)
[3]粘滑瓢宛転東撲。(粘滑の瓢は宛転東撲)
[4]西捺□□□□□。(西捺□□□□□)
[5]唯拈竹竿持揺頭。(唯竹竿を拈じて揺頭を持す)
すべてで三十五字あるが、これを七字ずつに分けている。『大日本史料』でも同じ断句になっているが、[4]を西捺□□□勧君としている。勧君は退蔵院古謄複本で補ったものである。
次に『禅林画賛』では、
[1]孟八郎漢是掠虚。(孟八郎漢は是れ虚を掠ふ)
[2]操瓢□走趁鮎魚。(瓢を操り□走して鮎魚を趁ふ)
[3]粘滑瓢宛転。(粘滑の瓢は宛転)
[4]東撲西捺。(東に撲ち西に捺へて)
[5]□□□□□。(□□□□□)
[6]唯拈竹竿持揺頭。(唯だ竹竿を拈り持って頭を揺する)
七・七・五・四・五・七となっている。ここでも、『大日本史料』で補われている勧君の二字は□□とされている。
原本の賛詩は上中下の三段に分けられており、下段の賛詩(詩一九から詩三〇まで)はすべて七言である。そのために下段は字数にあわせて十四字詰めの枡目になっている。このことから見て、この詩もまずは基本的には七言形式と見るべきであろう。そこで、最初の部分を七字で断句して並べると、一、二句は、
[1]孟八郎漢是掠虚。
[2]操瓢□走趁鮎魚
となり、福嶋氏および『禅林画賛』の場合と同じになる。「孟八郎漢」は道理のない、思慮分別のない男。「掠虚」は、うわべを取るだけで内実のないことである。
[3]以降を検討する。「東撲西捺」の語であるが、これは「東奔西走」「東窺西望」「東衝西突」「東扶西倒」「東話西語」などの例があるように、「東○西△」は「あちこちと」何らかの行動をすることであり、「東撲西捺」は、「あちこち(矢鱈滅多と)おさえつける」ことである。
『禅林画賛』の訳は「あっち打ちこっち捺え」となっているが、「撲」はここでは「打つ」「なぐる」ことではない。鮎を「なぐる」のではなく「おさえつける」のである(74)。
さて、福嶋氏の場合、第三句を「粘滑瓢宛転東撲」と確定しているために、「東撲」と「西捺」とが切れることになっているが、これは適当でない。「東○西△」の四字の結合度合いを重視するならば、『禅林画賛』のように「東撲西捺」と固定されねばならない。よって三、四句以降は、
[3]粘滑瓢宛転
[4]東撲西捺
[5]□□□□□
となる。七言形式に拘って検討してみよう。[3]の「粘滑瓢宛転」は字数の上からは二字少ないことになる。この五字の中で、熟語として固定できるのは「粘滑」と「宛転」である。「宛転」は、まろやかな物がコロコロと転がるさまを言う語であり、丸い瓢箪がまろぶさまを言うのに相応しい。したがって「瓢宛転」の三字は固定されよう。
残る「粘滑」は、粘液でネバネバしてヌルヌルであるさまをいう。『禅林画賛』では「粘滑の瓢は宛転」と訓じ、「つるつるの瓢はぐるぐるまわって」と訳しているが、「粘滑」は「つるつる」というよりむしろ「ネバネバ」であろう。強いて訳しなおせば「ネバネバの瓢箪はコロコロ転がる」ということになる。
しかし、瓢箪は、たとえ生のそれであっても「粘滑」ことに「粘(ネバネバ)」とは関わらない。この瓢鮎図に登場する物で「粘滑」の特質をもつものは鮎魚以外にはあるまい。
他の七言の部分がそうであるように「四字+三字」に分かれることがまず考えられる。下の三字は「瓢宛転」になる。したがって、残る四字部分は「□□粘滑」となる可能性があり、□□は、粘滑という性情をもった物体が主格とならなくてはならない。そこで、第三句を、かりに、
[3]□□粘滑瓢宛転
とする。「粘滑」の「粘」は詩二五、二六に出るように鮎魚の性情である。したがって□□が「鮎魚」であれば、「鮎魚は粘滑、瓢は宛転」となり、意味の上からは適合することになり、きわめて都合がよい。
ところが、原本ではこの□□の二字が入るべきスペースはない。この詩画軸ができた最初から、現状の字詰めどおりであったとするならば、この[3]の部分は「粘滑瓢宛転」と、五字だけにならざるを得ないだろうが、それでは、上に見たように意が取れない。
この矛盾を解決するには、逆から推論するしかない。意味が通じない、ということは、この詩画軸が完成した時には、現状の字の配置ではなかったことが考えられはしないか。すなわち、後世の修復の際に何らかの混乱があったのではないか。
「瓢鮎図」はいま京都国立博物館に寄託されている。筆者はこの原本を精査する機会を得ることができた。原本を熟覧するに、詩三一が書かれた部分はもっとも剥落破損が激しいところである。にも拘わらず、罫線は明瞭に描かれている。これは、この罫線が補修の際に引かれたものだからであろう。原本のこのような状態からすれば、剥落した断片が張り付けられ補修される段階で、何らかの混乱があったことも想定されよう。
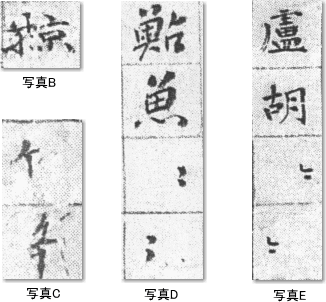
「掠」字のテヘンの部分には、修復の際にできたと考えられる、かなり大きなズレがあるし(写真B)、「竿」字の竹冠の部分もバランスがよくないなど、修復段階で起こったと思われる混乱の痕跡が残っている(写真C)。
例えば問題の箇所は、原本では「鮎魚」と書かれていたのではなく、詩一〇(写真D)、詩一七(写真E)などに見られるように、この部分は踊り字で書かれ「〃〃粘滑瓢宛転」となっていた可能性も考えられはしないか。
大胆な仮説ではあるが、実はそんな推測が許されるような事情があるのだ。退蔵院には江戸期のものと思われる模本が現存するが、その賛詩の部分に重大な異同が確認できるのである。賛詩三〇の部分である。賛詩三〇の最下部分にある六字、「欲抽身」と「枉苦辛」とが模本には書かれていないのである(写真F・G)。
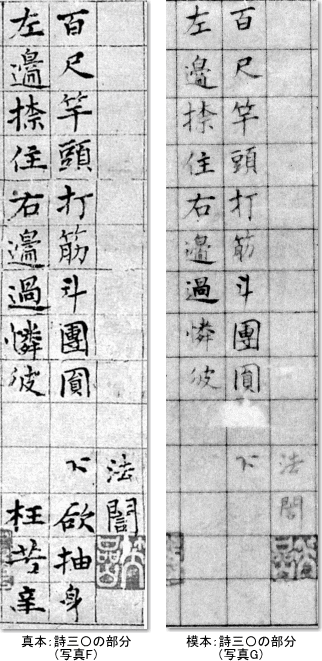
これはいったいどうしたことか。考えられる理由は二つある。
(1)模本の制作者が何らかの理由で写し忘れたか、あるいは意図して書かなかった。
(2)模本が制作された段階では、この六字は原本にはなかった。
模本における賛詩の模写状態を見るに、書体も極力似せようとした努力のあとが見られるし、欠損部分も比較的忠実に書かれ、全体として丹念に写されていることがわかる。これからすれば、(1)の理由は考えにくく、(2)の理由のほうが可能性が高いと考えられる。賛詩全体の中で左の最下部はもっとも破損の大きい部分で、何回かの補修を経ているように思われる。また、模本にはないのに原本には書かれている詩三〇の「欲抽身」と「枉苦辛」の六字分は、他の部分と比べて墨色がかなり濃いように見えるので、この部分が後に書き加えられた可能性も想定されるのであるが、そのことは科学的検査をすれば判明することであろう。
この六字を含んだ詩三〇は、七言詩として、語法の上から見ても矛盾することなく解釈できるものになっている。したがって、万一、この六字が後に書き加えられたものだとしても、その六字は何らかの依拠するに足る資料に拠ったことが考えられる。
もし、賛詩三〇の二十八字全部を記録した資料が、後から発見され、それによって加筆修正したのであれば、原本に欠けている三字分、すなわち「団円□下欲抽身」「憐彼□□枉苦辛」の部分も補ったはずであろうから、その可能性は少ない。
現に、原本にも模本にも上の三字分が欠如していることからすれば、欠損した六字分のみの剥落部分のあることが後になって判明して、これによって補修したのではないかとも思える。もう一つの可能性としては、三字分が欠損した元の状態を写した資料の存在が出現して、これによって六字の部分を加筆したことも考えられよう。
瓢鮎図の修復は、おそらくは江戸期に数次にわたって行なわれたものと思われるが、修復の段階でいくつかの混乱があったこと、ことに、この詩三〇およびそれに隣接する詩三一の部分での混乱があったことが充分考えられるのである。
詩三一の断句の検討に戻る。第四句は福嶋案のように「粘滑瓢宛転東撲」とはなり得ないのであるから、「東撲西捺」は後ろにある「□□□」と結合することになる。すなわち、
[4]東撲西捺□□□
となる。そして、後には「□□唯拈竹竿持揺頭」が残るが、この部分は後で考察するとして、まず、これまでに見た一~四句を整理し、欠損部分を検討して見る。
[1]孟八郎漢是掠虚
[2]操瓢□走趁鮎魚
[3]粘滑瓢宛転
[4]東撲西捺□□□
第二句「操瓢□走趁鮎魚」は一字が欠けている。「□走」が二字で固定されるとしたら、意味の上からは「乱走」「漫走」などが考えられる。「瓢を操って乱りに走り、鮎魚を趁う」か「瓢を操って漫に走り、鮎魚を趁う」である。
次に、[1]~[4]を押韻の上から検討してみる。一、二句の最後の字は「虚」「魚」であり、上平声「六魚」の韻である。先行する賛詩で上平声「六魚」の韻が用いられているのは次のとおりである。([ ]はふみおとし)。
詩三、[甚]・魚・余
詩七、[滑]・魚・蘆
詩一〇、魚・蘆・廬
詩一一、[去]・魚・渠
詩一二、余・魚・渠
詩一三、[滑]・如・渠
詩一八、[子]・魚・渠
詩二九、余・漁・魚
これからすれば、詩三一も「六魚」の韻をふんでいる可能性が高い。とすれば第四句「東撲西捺□□□」の脚字に採用されるべき字は次のうちのいずれかである。
居虚魚漁車書諸如徐除疎初余据裾鋤嘘於猪儲且舒渠輿胥疏梳閭墟驢淤廬
前出の詩での韻字を頻度順にいえば、
「魚」 … 7
「渠」 … 4
「余」 … 3
である。「魚」は[2]で使われているので、たとえば「渠」を入れれば、
[4]東撲西捺□□渠
となる。これを意味の上からして推理するならば「東撲西捺争奈渠(東に撲ち西に捺うるも、渠を争奈せん)」などが候補の一つとして考えられてもいいのではないか。

残された「□□唯拈竹竿□揺頭」の部分を検討する。
□□の二字欠損部分は、『大日本史料』では退蔵院古謄複本によって勧君と補注している。この部分を原本で詳細に観察してみよう(写真H)。最初の字はかなりの筆跡が残っていて手がかりがある。右側は「力」に近い。左側も下部に残された筆画は「隹」に近い。「力」と「隹」を構成部分に含む漢字である。それは「勧」字である。また「持」と読まれている字は、ヘンが欠損していて断定できないので、いまここでは□とする。すなわち、
[5]勧□唯拈竹竿□揺頭
となる。「唯拈竹竿□揺頭」は七字(四字+三字)としてまとまりそうに思われるので、これを七字一句とすると、「勧□」だけが残る。「勧□」も二字だけで独立した意味を持つはずであるから、「勧君」などが考えられ、退蔵院古謄複本と合致することになる。以上、推理したところをあわせると、
[1]孟八郎漢是掠虚
[2]操瓢走趁鮎魚
[3]粘滑瓢宛転
[4]東撲西捺
[5]勧
[6]唯拈竹竿□揺頭
となる。最後に「□揺頭」の三字であるが、この部分は退蔵院蔵古謄本で「持揺頭」と読まれ、これが『大日本史料』以降、すべての翻刻において踏襲されている。
『禅林画賛』ではこの句を「唯だ竹竿を拈り持って頭を揺するのみ」と訓じて、「竹竿を手に首を振るばかり」と訳されている。「持」は手でもつことである。瓢鮎図に登場する動物は男と鮎である。鮎には手がないから「持つ」ことはできない。したがって「竹竿を手に首を振る」のは図に描かれた男ということになる。つまり、『禅林画賛』の解釈によれば「男が竹を手に持って自分の首を振る」という意味になる。かかるナンセンスを漢詩にする必要があるだろうか。
ふたたび原本のこの部分を熟覧して見よう(写真A左端)。欠損はあるものの「揺頭」の部分は判然としているので確定してよい。「揺頭」という語は先行する賛詩には見られなかったものだが、詩二〇には「擺尾」という語がある。
この二つを結合した「揺頭擺尾」という表現はしばしば禅録に見られるものである。魚が流れを「頭をふり尾をふって」勢いよく溯行したりする時の動作を表わす語である。禅録でもっとも有名なのは、詩二〇で引いた『聯灯会要』の「臨済門下有一赤梢鯉魚、揺頭擺尾、向南方去」の一段である。

かくして「揺頭」が確定すると、□を「持」と解読するのはいよいよ穏やかではない。左のヘンは欠損して右のツクリだけが残っている(写真I)。ツクリは明らかに「寺」である。ツクリが寺になっている漢字には、侍・待・峙・持・時・特・詩がある。
左のヘンは欠損してはいるものの、わずかに残されている起筆部分の位置および角度から見るに、これはテヘンではない。テヘンならばすぐ下にある「揺」の例がある(写真J)。ニンベンないしギョウニンベンの初画であろう。
候補としては「待」「侍」にしぼられるが、「侍」では意不通である。よって「待揺頭」と考えられる。「待」字は、詩四に「待跳上竹」と出るが、それと同じ「待」である。訓ずれば「揺頭するを待て」となる。
上の『聯灯会要』の例でみた、いわゆる「臨済門下の赤梢鯉」は、「他後、活龍に変る可き機」(無著道忠『五家正宗賛助桀』)のことであり、「揺頭」はそのしぐさである。鮎が勢いよく頭を揺って、猛烈な勢いで竹を登って来るところである。
詩一六には「応待有龍門登」、また詩二一には「定鼓風雷飛化龍」、さらに詩二九には「応笑龍門点額魚」とあるが、これはいずれも鯉が龍門の滝を登って龍となる「登龍門」の事をふまえたものであり、同じ魚類の鮎が主題となっている本画賛にはふさわしいものである。
ここの「待揺頭」も、その鯉のように、ナマズが滝ならぬ竹を登ることをいうのであり、同じ発想にもとづくものである。
以上の推測によって、詩三一の欠損部分を補い、これの訳を試みてみよう。
孟八郎漢是掠虚、
(孟八郎 の漢、是れ掠虚 )
操瓢走趁鮎魚。
(瓢を操って漫 りに走って鮎魚を趁 う)
粘滑瓢宛転、
(鮎魚は粘滑、瓢は宛転 )
東撲西捺。
(東撲 西捺 、渠 を争奈 せん)
勧君、
(君に勧む)
唯拈竹竿揺頭。
(唯だ竹竿を拈 って揺頭 するを待て)
この詩三一は最後のものである。島尾新氏は、この最後の詩を書いた厳中周噩が「詩を題する人々の人数を決めて人選を行い、詩形の割り振りをするマネージャー」であろうとし、「彼は、最後の余白を(責任をとって)ひとりだけ異なる詩形で埋めている」と指摘している(島尾前掲書40頁)が、筆者もその説に賛同する。
厳中周噩の詩は、これまでの詩と同じように、七言四句を作り、これにさらに「勧君、唯拈竹竿待揺頭」を付け加えたものである。推測した詩三一を原本の上に置き直してみると、次のようになる(括弧内が現状の配置である)。
孟八郎漢是掠虚操瓢走趁鮎魚
(孟八郎漢是掠虚操瓢□走趁鮎魚)
粘滑瓢宛転東撲西捺
(粘滑瓢宛転東撲西捺□□□勧君)
勧君唯拈竹竿揺頭
(唯拈竹竿□揺頭)
七言四句を一行十四字詰の枡で区切られたところに書けば、おのずと十四字詰二行にならねばならない。そして、この七言詩は先行する七言詩と脚韻が合致することが望ましい。上の虚・魚・渠であるならば、その条件に合致することになる。
そして、最後に余った一行に厳中周噩は「勧君、唯拈竹竿待揺頭」と書いたのであるが、この九字は、トリとして一連の賛詩の連作を総括するのにふさわしい意味を含んでいよう。
鮎が頭を振って竹に上るのは、法界に周徧している真心に超入することであり、心で心を捉えようという、果てしない徒労から脱却することだからである。
【訳】大馬鹿者が、ありもせぬ虚をもとめて、瓢箪を手にやたらと鮎を追いまわす。
鮎はヌルヌル、瓢箪コロコロ、やたらめった抑えまわってもどうにもならん。
それよりは、竹をおさえ、鮎が(龍門を登る鯉のように勢いよく)尾を振って登って来るのをお待ちなさい。